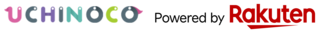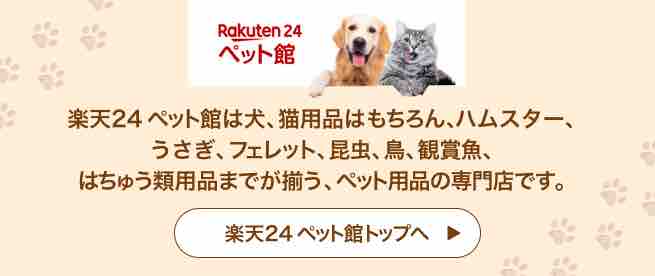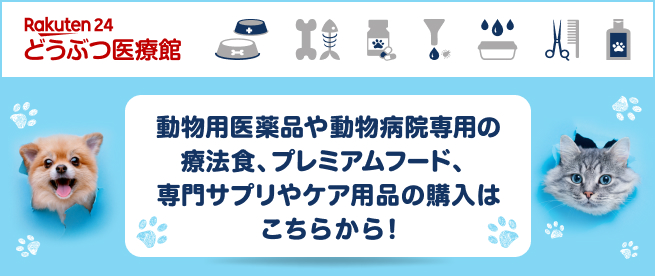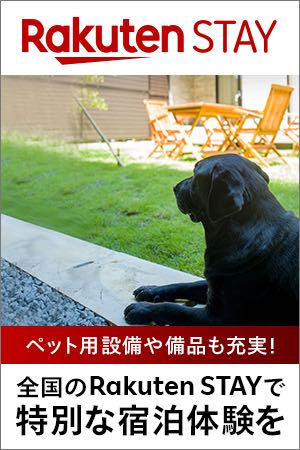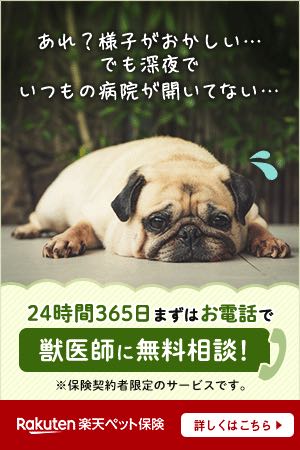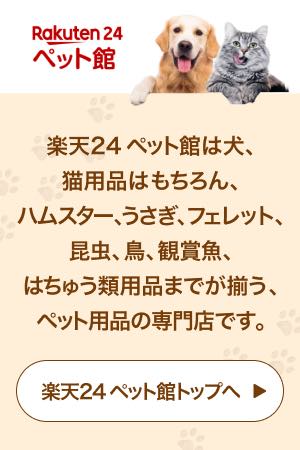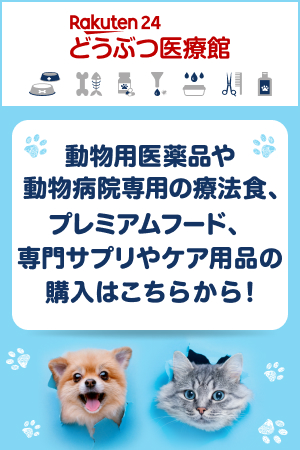補助犬の種類・仕事内容

出典:https://www.shutterstock.com/
まずは本題である、補助犬の種類を解説します。
併せて、それぞれの補助犬の仕事内容についても見ていきましょう。
盲導犬
視覚障害のある人が、安全に目的地までたどり着けるようにサポートするのが、盲導犬です。
盲導犬がハーネスをつけて歩いている姿を、一度は見たことがあるでしょう。
盲導犬は、段差があったら止まって教えたり曲がり角で止まったりして、盲導犬ユーザーの安全を守ります。
ただし、盲導犬は目的地まで案内することが目的ではなく、あくまで安全に歩くことができるようにサポートすることが目的です。
そのため、盲導犬ユーザーは頭の中で目的地までの行き方を覚える必要があります。
盲導犬ユーザーが頭の中で覚えた地図を使って、ハーネスから伝わってくる盲導犬からの情報を組み合わせることで、目的地までたどり着くことができるのです。
ちなみに、盲導犬は辛抱強く楽しめる性格の犬種が求められるため、ラブラドールレトリバーが圧倒的に多いです。
聴導犬
聴導犬は、聴覚に障害のある人の代わりに、音が鳴った時に知らせる仕事をしています。
人間が生活する上で必要な音といえば、電話の着信音や家のチャイムなどでしょう。
もしもこれらの音が鳴った時は、聴導犬が聴導犬ユーザーの足や身体にタッチして音が鳴ったことを知らせた後に、音源まで誘導します。
また、火災報知器や車のクラクションなど、緊急時の音に対してもしっかりと反応してくれます。
聴導犬は盲導犬のようにユーザーの身体を引っ張るような身体の大きさは求められていないため、音に鈍感でさえなければさまざまな犬種が活躍することが可能です。
介助犬
補助犬は、先述した盲導犬と聴導犬、そして介助犬の3種類しかありません。
介助犬は、身体に障害のある人の代わりに、ドアの開閉や物を持ってくるなど、生活の手助けをしてくれます。
また、毎日の着替えや起き上がりなどを介助するなど、ユーザーの指示に合わせて行動します。
ちなみに、介助犬はユーザーの生活全般を任されるため、力の弱い小型犬は不向きでラブラドールレトリバーなどの大型犬が活躍することがほとんどです。
補助犬になるために必要な訓練とは?

出典:https://www.shutterstock.com/
補助犬は、どんな犬でもなれるわけではありません。
次に、補助犬になるために必要な訓練をご説明します。
健康状態や性質も求められる
補助犬には、向き不向きがあります。
先述したように、人間の生活全般を手助けする盲導犬や介助犬は、ラブラドールレトリバーなどの大型犬がほとんどです。
また、補助活動がスムーズにできる性質であることも求められます。
補助犬の候補犬の選抜が終わったら、それぞれ訓練に進んでいきます。
盲導犬は1歳まで一般家庭で生活する
盲導犬の場合は、候補犬となってから生後2ヶ月から1歳になるまで、パピーウォーカーと呼ばれるボランティア家庭で過ごします。
この約1年で、盲導犬の候補犬は、人間社会で暮らすためのルールを学ぶのです。
ちなみに、期間には差がありますが聴導犬や介助犬にも、ボランティア家庭で過ごす期間があります。
基礎訓練
ボランティア家庭での暮らしが終了した後は、補助犬の仕事に合わせた訓練を行います。
しかし、はじめのうちは呼びや伏せなどの基本的な訓練から始めます。
また、何よりも仕事を優先できるように、美味しそうな食べ物や楽しそうな出来事を無視できるような訓練も行い、補助犬としての役割を全うできるようにするのです。
それぞれの役割に合わせた訓練を始める
基礎訓練が完了したら、それぞれの役割に合わせた訓練を行います。
盲導犬であれば、視覚障害のある人と街中を歩くタウンウォークを行い、聴導犬や介助犬は「介助動作訓練」という物を拾ったり運んだりする、ユーザーの日常生活を手助けするような動作を身につける訓練をします。
ユーザーとの訓練
基礎訓練やそれぞれの役割に合わせた訓練が完了したら、とうとうユーザーとの訓練を行います。
実際にユーザーからの指示を受けて、どんな場所であっても指示どおりに動けるかを訓練で強化していきます。
もちろんユーザーとの信頼関係も大切になってくるため、ユーザーと補助犬が訓練センターでいっしょに生活したり、ユーザーの自宅で実際にサポートしたりもしていくでしょう。
補助犬の引退後の生活

出典:https://www.shutterstock.com/
補助犬は、高齢などの理由でいつかは引退してしまいます。
補助犬が引退した後は、どのような生活をするのでしょうか?
補助犬は10歳前後で引退する
補助犬は、10歳前後で引退することが多いです。
それまでは、10年近くユーザーとともに生活を支えてきたわけですが、引退後はユーザーが別の補助犬と生活をしていくことになります。
引退後の補助犬は大型犬が多いため、人間の年齢に換算すると70歳前後と、シニア犬と呼ばれる年齢になっています。
余生はボランティア家庭で過ごす
引退後の補助犬は、ボランティア家庭で過ごします。
いままではユーザーのためにすべてを捧げてきた犬たちなので、次は自分が幸せになる番です。
しかし補助犬たちはユーザーに仕えることを幸せに感じるため、引退後も生活環境によってはそのままユーザーといっしょに暮らしていることもあります。
もちろんユーザーは引退後の補助犬といっしょに出かけることはできないことから、2頭目の補助犬と出かけようとする時に、やきもちを妬いてしまうこともあるようです。
何はともあれ、引退後の補助犬の余生は、仕事のことを考えずにのんびりと自由に過ごしていることが多いでしょう。
補助犬は障害のある人のために働いている

出典:https://www.shutterstock.com/
補助犬は、盲導犬と聴導犬、そして介助犬の3種類です。
それぞれの補助犬は、身体に障害のある人の代わりに、手となり足となって働いています。
もちろん補助犬になるために向き不向きがあるため、訓練をしても補助犬になれないこともあるでしょう。
そして10年近くの仕事を終えた後は、ボランティア家庭でのんびりと余生を過ごします。
どんな人でも安心して生活ができるのは、補助犬などの支えがあってのことなのかもしれません。
著者情報

けんぴ
若い頃はドッグトレーナーとして、警察犬の訓練やドッグスポーツなどを行う。
それらの経験を活かし、ペット系ライターとして活動中。
現在はすっかり猫派となる。
好きな犬種・猫種はボーダーコリーとノルウェージャンフォレストキャット。