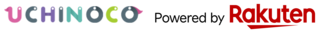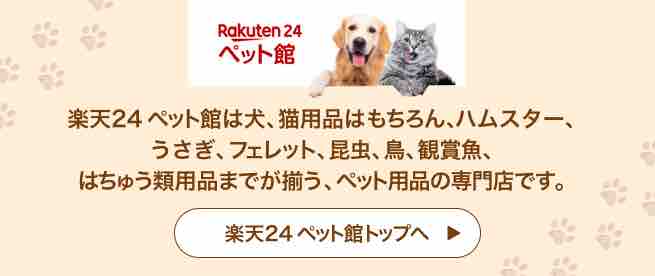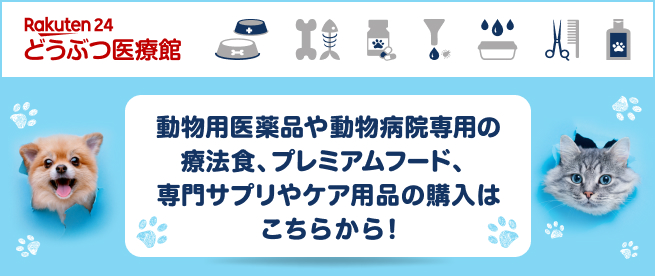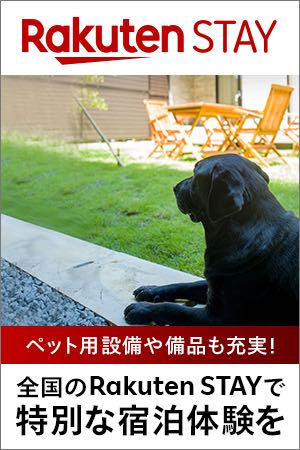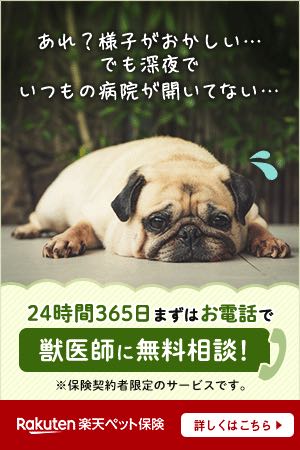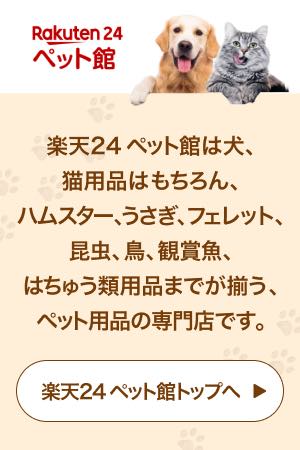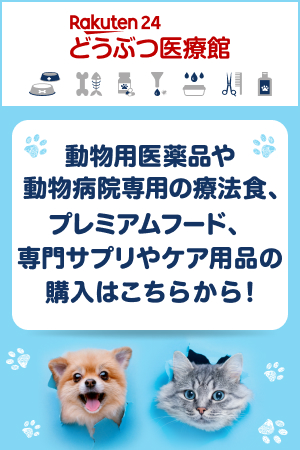犬の皮膚に寄生するダニは、犬の体にあらゆる影響を及ぼします。今回は、犬に寄生するダニの種類や、主な症状についてご紹介しましょう。
1.犬にダニを見つけたらどうする?
愛犬にダニを見つけた場合、すぐにつぶしたり、手でつかみ取りたくなると思います。しかし、そのような行為は行わないようにしましょう。
もし、このようなことをした場合、ダニは、口で犬の皮膚に噛みついて固着して血を吸い、無理に犬の体から引きはがそうとすると、病原体を持っているかもしれないダニの頭部や口などが犬の体内に残ってしまう恐れがあり、化膿してしまう可能性があります。
こうしたリスクを避けるため、動物病院へ連れていく、またはダニが犬の皮膚に喰いついていない場合のみ、専用のピンセットで取り除くようにしましょう。
2.犬に寄生するダニは4種類

出典元:https://www.shutterstock.com/
犬に寄生するダニは、マダニ、ニキビダニ、ヒゼンダニ、ツメダニの4種類です。この中だと、マダニがとても有名で、かつ危険性の高いものと言われています。しかしマダニにとどまらず、これらはどれも犬の体に影響を及ぼすものなので注意が必要です。
3.マダニの症状・駆除方法

出典元:https://www.shutterstock.com/
マダニは他のダニと明らかに違う特徴を持っており、犬の血を吸って生き延びます。吸血して膨れ上がったマダニは、大きいものならば約1cmにもなるほど。重さは、吸血前の約200倍と言われています。マダニがたくさん住みつくと、犬は貧血症状を起こしてしまうでしょう。また、吸血時に吐き出す唾液が原因でアレルギー性皮膚炎にかかると、かゆみが伴うこともあります。
愛犬にマダニが付着しているのを見つけた場合、無理に取ることだけはやめてください。マダニを強く引っ張ると、顎だけが犬の皮膚に残り、そこから皮膚炎を発症することがあります。ピンセットで慎重に取り除くか、もしそれが心配ならば医師に相談するのが良いでしょう。医師が処方してくれた薬なら、簡単にマダニが駆除できるので安心です。
4.ニキビダニの症状・駆除方法

出典元:https://www.shutterstock.com/
ニキビダニは0.2~0.3ミリほどの小型のダニで、別名で「毛包虫」と名付けられています。その名の通り、犬の毛包や皮脂腺に住みつきやすいダニで、目、口の周り、そして前足の先の方に寄生しやすいです。ニキビダニが増殖すると脱毛の症状が表れ、症状が悪化すると皮膚がただれてしまいます。そのような皮膚の状態から二次感染し、かゆみを伴うケースもあるので、早期治療が肝心です。
ニキビダニは小さいため、どうしても手で取ることはできません。病院で処方された薬を投与して、症状を和らげていきます。ダニの駆除薬を使っても、治療には最低1ヶ月ほど必要。それでもすべてのニキビダニを駆除し切れないかもしれません。症状が重い場合は1年以上も投薬を続けなければならないため、発症してしまった以上は根気強く治療を続けましょう。
5.ヒゼンダニの症状・駆除方法

出典元:https://www.shutterstock.com/
ヒゼンダニは犬の皮膚の中に寄生するダニの種類で、体長は0.2~0.4mm程度です。お腹などの毛がない部分に寄生しやすく、耳に住みつくものをミミヒゼンダニと呼びます。ヒゼンダニの厄介なところは、皮膚の中に潜り込むとそこからトンネルを掘って生活する点です。そのため強いかゆみを発症し、皮膚病を引き起こしてしまいます。
ヒゼンダニの体の小ささでは、手で取り除くことができないため、投薬によって症状を改善していきます。ダニ駆除薬やかゆみを抑える抗生剤などを使えば、すぐに症状が軽くなりますが油断は禁物です。ヒゼンダニの卵が皮膚に残っていると、再発する恐れがありますので、1週間ほどは薬の投与を続けましょう。その後は医師の指示に従って薬を続けてください。
6.ツメダニの症状・駆除方法

出典元:https://www.shutterstock.com/
ツメダニは、前足に大きな爪を持っていることからその名がつけられました。その鋭い爪で犬の皮膚に取りつき、体液やリンパ液を吸います。主な症状としては、とにかくフケが出てしまうこと。フケの中に動いているものを見つけたら、それはツメダニでしょう。その他、激しいかゆみや皮膚のただれも発症し、全身のあらゆるところに寄生する可能性があるダニです。
ツメダニの駆除では病院で処方された薬、そしてシャンプーが良いとされています。症状の治りを早くするためには、全身の毛をカットするのも効果的です。ツメダニ自体は薬ですぐに取れてしまいますが、卵も一緒に駆除させるためには、長期間の薬の服用が必要になるでしょう。
7.ダニから守るためにできる予防法

出典元:https://www.shutterstock.com/
愛犬の健康のためにも、なるべくダニが寄生するのを予防してあげましょう。対策としては、主に次の2つがあります。まずは、散歩に出かけた時など外へ出た場合、体にダニがついていないか確認することです。草むらに多く生息するマダニは、目視でも確認することができます。家へ入る前に、いったん体中をチェックしてあげるだけでも効果的です。他の犬と接触があった場合は、その犬から感染することも十分ありえますので、少し注意する必要があります。
また、部屋の掃除を定期的に行うだけでも、ダニの増殖を防ぐことは可能です。犬の小屋やえさ入れ、タオルなどを清潔に保っていれば、万が一ダニが寄生してしまっても重症化を食い止められるかもしれません。ダニは50℃以上で死滅するため、熱湯処理を行うとより増殖を防げます。
8.犬のダニ対策グッズの選び方
ダニから大切な愛犬を守るための2つの対策を紹介しましょう。
ブラッシング
ブラッシングを行うことで、愛犬に付着したダニを発見することが可能になります。なお、室内でブラッシングを行うと室内にダニが生き延びてしまうリスクがあるため、ブラッシングは玄関の屋外側で行うように配慮しましょう。
駆除薬
駆除薬には、2種類のタイプがあります。
錠剤薬
犬が服用しやすいようにチキン風味やビーフ味などがあります。投薬後4~8時間後に全身に薬の効き目が行き渡り、体に付着するマダニの駆除ができます。効果は1か月持続と3か月持続のものがあります。ただし、アレルギー体質の犬は服用できない場合があるため、動物病院で相談しましょう。
スポット薬
アレルギー体質で投薬できない犬にも服用できるタイプの薬です。首の後ろに液体の薬を垂らして使用しますが、投薬後約24時間で全身に薬の効果が行き渡ります。投与の前後数日はシャンプーを控える方が無難です。効果は約1か月持続します。
9. ダニ駆除後にやるべき3つのこと(再発防止策)
愛犬のダニ駆除後に、再発を避けるためにやるべきことを3点紹介します。
部屋の掃除
ダニの卵や幼虫は、ソファー、布団、カーペット、カーテンの隅などに潜んでいます。また、ペットの布団やマットなどにも潜みやすいため、これらの場所に対して掃除機をかけること、粘着テープのコロコロの使用や、関係するリネン類の定期的な洗濯と天日干しを行うことが肝要です。
熱処理
ダニが死滅するのは20分間50℃以上の環境となるため、シーツや毛布、クッションなどは熱湯洗濯などを行い、季節が変わるごとに対応しましょう。
殺虫剤の使用
殺虫剤は、ダニの成虫に効果を発揮する反面、卵や幼虫への効果は限定的になります。すでに紹介した駆除薬や部屋の掃除と併用することが大切です。
10.ダニを防いで愛犬の命を守る
ダニの寄生は、愛犬の命に関わることでもあります。一命は取りとめても、ダニの種類によっては長期間の治療が必要になることも珍しくありません。何歳になってもダニが寄生する可能性は十分あるので、常に予防を行い、こまめに愛犬の状態を見てあげることが大切です。
著者情報

UCHINOCO編集部
UCHINOCO編集部では、ペットに関するお役立ち情報をお届けしています。