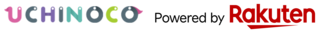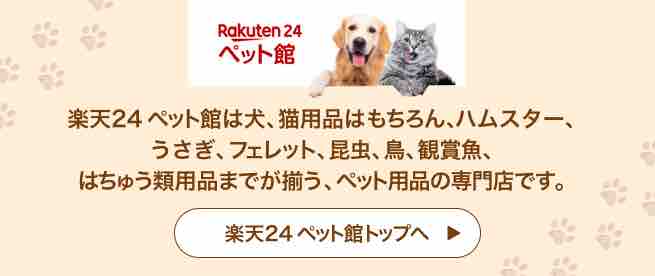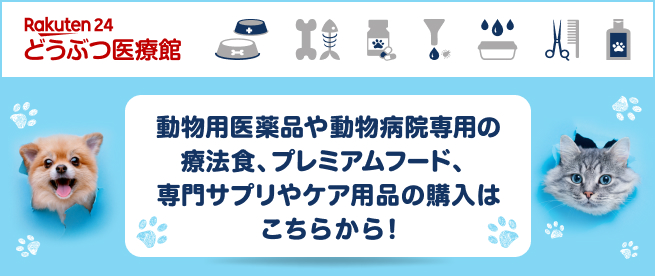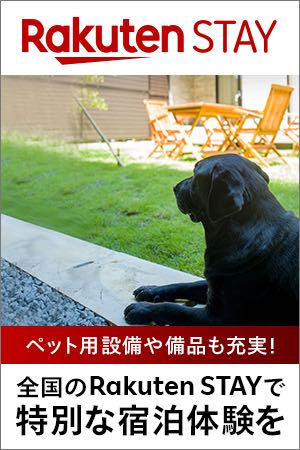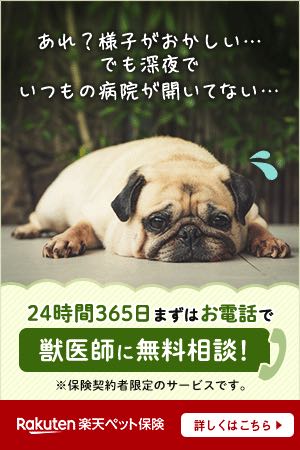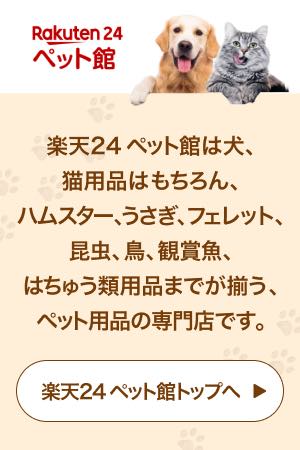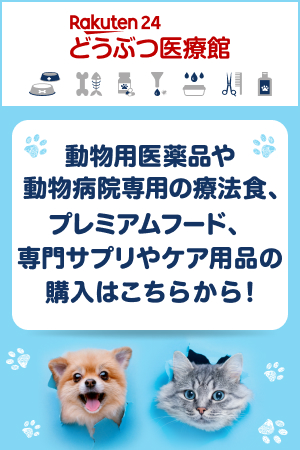1.豆柴の基本情報
JKC(ジャパンケンネルクラブ)のスタンダード基準に当てはめると、豆柴の基礎犬の柴犬の場合には体高より体長が長いことが特徴になっています。そして、耳は小さめで立っていることなどが基準です。また尾は巻いていて、短い毛にダブルコートという柴犬の基準をすべて引き継いだ形をコンパクトサイズにしたものが豆柴です。
豆柴は柴犬とほぼ同じ特徴を持っています。サイズこそ違いますが、原則として柴犬よりもより小さいことが基準です。よく言われているのが、小ぶりな「柴犬のメス」と「豆柴のオス」はほぼ同じサイズだということです。
2.豆柴の特徴や性格について

出典元:https://www.shutterstock.com/
「豆柴=柴犬」なので、気質や性格はほぼ同じです。その中でも特に自立心が強いところは、見かけのかわいらしさとは反比例するようです。小さい体格をしていても家族に甘えることも少なく、クールな気質をしています。これは豆柴と暮らして最初に飼い主が感じることのようです。
豆柴は、見かけによらず強い服従心と忠実さを持ち合わせています。そして、保守的で自分の周囲を守ろうとする防衛心が強いので、いろんなことに警戒し吠える場合があります。
また、テリトリーには強いこだわりがあるので、そのテリトリーを勝手に侵すような人や犬に対しては、獰猛な態度を示すことがあるので注意をしてください。一方で、飼い主が十分にしつけをしないでただ甘やかしてしまうことで、心身ともに未熟な成長を遂げる豆柴もいます。こうなってしまうとどうしても飼い主への依存心が強くなってしまいます。
柴犬もそうですが、温厚さや頑固さなどの性格も幅広く、豆柴は少し我が強いのでしつけには飼い主の粘り強さが必要なことも知っておいてください。大切なことは飼い主との良好な信頼関係です。そして、けじめのある上下関係を教えてあげることなのです。
3.豆柴の歴史について
豆柴の歴史はそれほど古くはありません。比較的新しく昭和30年頃となっています。残念ながら日本犬保存会やJKCでは、豆柴は犬種として認めないという姿勢を示しているようです。なかなか基準が難しいのですが、団体側の姿勢にも一理あるようです。
その一方で、天然記念物柴犬保存会においては豆柴を認める姿勢を示しています。特に血統書などの発行については、日本社会福祉愛犬協会が責任を持っています。
4.豆柴の気を付ける病気について
柴犬同様に豆柴も皮膚疾患の多い犬種です。ホルモンによるものや、真菌が原因になるものなどさまざまですが、その中でもアレルギーが原因となっている皮膚炎も意外と多いのです。
かゆみを訴えているような場合には特によく観察をして、こまめに皮膚のチェックとブラッシングを行うことが大切です。元々アレルギー疾患が多い犬種ですので、治りにくい皮膚炎を発症したときには、動物病院でのアレルギー検査も必要になります。
5.豆柴の食事について
基本的にアレルギーを起こしにくいグレインフリーのドッグフードを取り入れて、日頃からアレルギー対策を講じておくことは大切なことです。そして、豊富な動物性タンパク質を含んでいるドッグフードや、皮膚の健康状態を保つために「サーモンオイル」や「亜麻に油」という成分にも注目をしてドッグフードを選べば間違いないでしょう。
人工添加物や穀物も使用されていないので、安心して愛犬に与えることができます。
著者情報

UCHINOCO編集部
UCHINOCO編集部では、ペットに関するお役立ち情報をお届けしています。