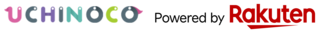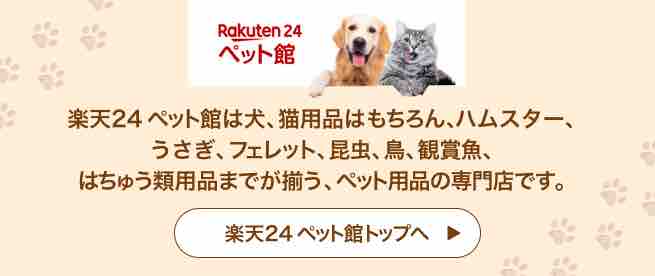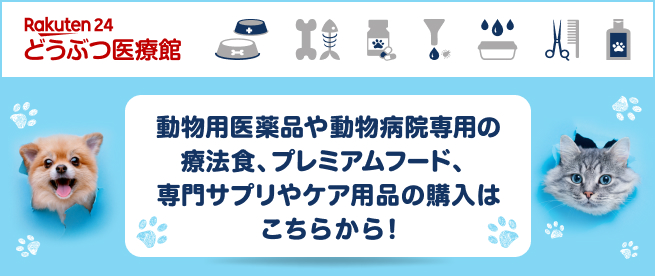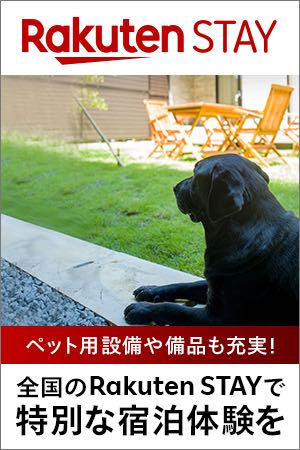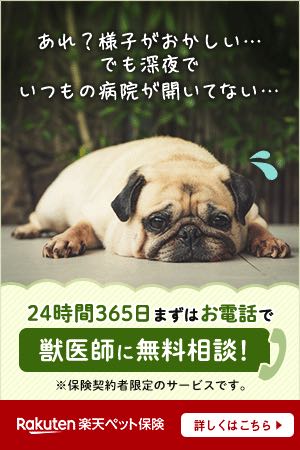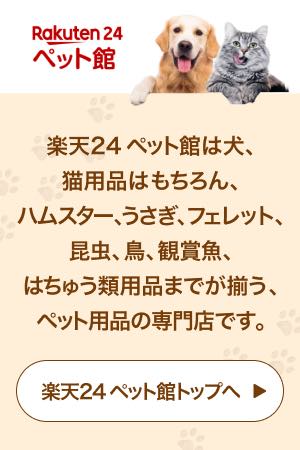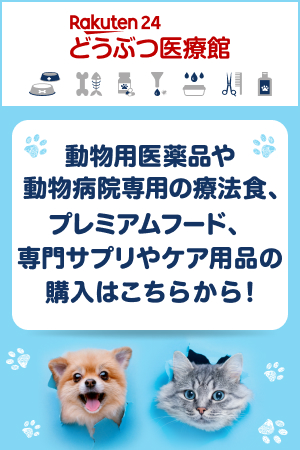中型犬の平均寿命は何歳?

出典:https://www.shutterstock.com
一般社団法人ペットフード協会が公開している「令和6年(2024年)全国犬猫飼育実態調査」によると、中・大型犬の平均寿命は2024年で14.37歳です。
犬の健康を考えたフードの開発や医療の発達など進んでいるためか、犬の平均寿命は年々長くなっており、13.69歳だった2010年度の調査に比べると0.67歳ほど寿命が延びています。
なお、愛犬の性別によって平均寿命に差はほとんどないと言われています。
また、去勢・避妊手術を受けている犬の方が、未手術の犬よりも長生きしやすいとされています。
去勢手術を受けたオス犬は13.8%、避妊手術を受けたメス犬は26.3%平均寿命が長くなるという報告も出ています。
犬種で見る中型犬の平均寿命一覧

出典:https://www.shutterstock.com
一般的に小柄な犬種ほど寿命が長い傾向がありますが、同じ中型犬でも犬種によって具体的な平均寿命が異なります。
ここからは、中型犬の平均寿命について、主な犬種別にチェックしていきましょう。
柴犬
アニコムグループが公開している『家庭どうぶつ白書2024』によると、柴犬の平均寿命は14.7歳です。
同じ日本犬の一種である秋田犬が11.8歳、甲斐犬が13.2歳という結果から、日本犬のなかでも柴犬は特に長生きしやすい犬種といえるでしょう。
長生きしやすい犬種ではありますが、目やアレルギー性皮膚炎などの皮膚疾患のリスクが高い傾向にある犬種でもあります。
また、年齢を重ねるにつれて緑内障、心臓系の疾患などの発症リスクが高まります。
ビーグル
同資料によると、ビーグルの平均寿命は13.4歳です。
しかし元々イギリス産の猟犬として活躍していた犬種であることから、優れた運動能力とスタミナがあります。したがって、1日に必要な運動量が多く、長生きのためには運動不足にならないように心がけることが大切です。
また、他の犬種と比較した場合、チェリーアイ・第三癌瞼脱出・瞬膜炎等の疾患のリスクが高くなる傾向にあり、日々しっかり健康チェックしてあげましょう。
コーギー
一般的に「コーギー」と呼ばれる、ウェルシュ・コーギー・ペンブロークの平均寿命は12.3歳です。
コーギーが罹りやすい疾患としては、食欲旺盛ゆえに肥満になりやすく、その結果として、遺伝的要因と併せて、背骨と背骨の間に位置する椎間板への影響を与え脊髄神経を圧迫する椎間板ヘルニアがあります。
しかし、適切な体重維持に努めたり、背中への負荷を下げる行動を心がけることで、長生きする子も多く、日本には20歳以上生きたコーギーもいるようです。
フレンチ・ブルドッグ
フレンチ・ブルドッグの平均寿命は11.1歳です。
全犬種の平均寿命と比較しても寿命が短めですが、これは鼻が短い犬種(=短頭種)であることから呼吸器系の健康リスクが高いうえ、関節トラブルが起こりやすいとされている点にあります。
長生きするのが難しいとされていたためか、一般的に10歳を超えたフレンチ・ブルドッグは、シニア期を超えたライフステージにいるとして「フェアリー期」と呼ばれています。
しかしなかには17歳以上生きている子もいることから、健康状態や飼育環境などに配慮することでフレンチ・ブルドッグを長生きさせられるでしょう。
ボーダー・コリー
ボーダー・コリーの平均寿命は13.0歳で、中型犬のなかでは平均的な数値といえます。
しかし、イギリスのブランブルというボーダー・コリーが27年211日まで生きたことでギネス記録に残っていることから、健康管理を徹底していれば長生きしやすい犬種といえるでしょう。
なお、ボーダー・コリーにはさまざまな色の被毛の子がいますが、なかでも「ブルーマール」と呼ばれる子については「マール因子」を持つことから他の被毛の子に比べて遺伝的疾患を発症するリスクが高いとされています。
そのため、ボーダー・コリーを長生きさせるためには日々の健康チェックはもちろん、お迎えの際に遺伝的疾患の有無をチェックしておき、それぞれの子に合わせた飼育環境に整えることが大切です。
中型犬の年齢を人間に換算すると?

出典:https://www.shutterstock.com
犬は人間よりも早く年を取る動物であり、同じように1歳年を取った場合でも4~7歳程度多く年を取るとされています。
犬の年齢を人間に換算する場合、愛犬の体格によって計算方法が異なり、小型・中型犬の場合は「24+(年齢-2)×4」の計算式で算出できます。
最初の2年で人間における24歳になり、3歳以降は1歳ごとに4歳ずつ年を取っていくのが一般的です。
以下に中型犬の年齢と人間に換算した場合の年齢の目安をまとめていますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
≪中型犬の年齢と人間に換算した年齢の目安≫
・1歳:15歳
・2歳:24歳
・3歳:28歳
・4歳:32歳
・5歳:36歳
・6歳:40歳
・7歳:44歳
・8歳:48歳
・9歳:52歳
・10歳:56歳
中型犬の老化のサインは?

出典:https://www.shutterstock.com
一般的に中型犬は7~8歳になると「シニア期」に入ると言われています。
小型犬に比べて体格が大きいことから、比較的早く老化のサインが出てくる傾向にあるので、愛犬のライフステージに合わせた飼育環境を整えるためにも、サインを見逃さないことが大切です。
ここからは、一般的な中型犬の老化のサインについて解説します。
歩く速度が遅くなる
中型犬の代表的な老化のサインが「脚力の低下」です。
一般的に犬は加齢に伴い脚力が弱くなっていくため、シニア期になると普段の歩く速度が遅くなってくる傾向にあります。
さらに脚力が落ちてくると脚の筋肉で体が支えられなくなり、お尻が少し落ちているような体勢(または後ろ脚がハの字になった姿勢)で歩くようになります。
そのため、以前と同じように高い所から飛び降りたり、段差を駆け上がったりした際に骨折するリスクが高くなるため注意が必要です。
散歩中などでも、長距離や段差を嫌がるようになる子も少なくありません。
眼球の中心が白っぽくなる
中型犬の老化のサインは見た目にも表れることがあり、特に「目の中心が白っぽくなる」というケースが多くみられます。
これは核硬化症といって、犬の目のうちカメラのレンズのような役割を持つ水晶体という部分が、加齢に伴って圧縮されて硬くなり、白く見えるようになる状態のことです。
尚、見た目だけでは核硬化症と白内障はよく似ていて、一目見ただけでは区別がしにくい点には要注意!
白内障の場合は適切な治療が必要になるため、このようなサインが出てきたら一度病院へ相談しにいくことをおすすめします。
毛づやの低下・イボの発生
毛づやが悪くなってきた・イボが出てきたなど、愛犬の皮膚環境が変化してきた場合も、老化のサインと言われています。
中型犬は加齢に伴って皮膚の代謝が低下することから、被毛が薄くなったり皮膚にハリがなくなったりする場合もあります。
聴力の低下
視力だけでなく、聴力の低下も代表的な中型犬の老化のサインです。
愛犬への呼びかけに対する反応が鈍いときや、手を叩いて呼んだときに反応しなくなっているときなどは、聴力が低下している可能性があります。
聴力は犬にとって周囲の状況を把握するために重要な感覚であり、低下するとコミュニケーションや危険を回避するのが難しくなります。
中型犬が長生きするために飼い主さんができることとは?

出典:https://www.shutterstock.com
犬種によって平均寿命が異なるとはいえ、環境によってはさらに長生きする子も多くいます。
大切な愛犬と長く一緒に暮らすために、ここからは中型犬が長生きするために飼い主さんができることを紹介します。
愛犬の運動量に合わせた散歩
中型犬が健康に長生きするために、愛犬の運動量に合わせた時間・コースで散歩することが大切です。
近年は完全室内飼いの犬が多く、室内で過ごす時間が多いことから運動不足になる子も少なくありません。
特に中型犬は平均して1日に必要な運動量が多く、ボーダー・コリーやコーギーなどの活発な犬種は1回あたり1~2時間もの散歩が必要とされています。
運動不足は筋力の低下や肥満のリスクを招くだけでなく、ストレスの原因にもなります。
そのため室内で遊ぶだけでなく、愛犬に必要な運動量に合わせて散歩の時間・コースを長くしたり、定期的にドッグランを利用したりなどの工夫によって、十分に運動させてあげてくださいね。
栄養バランスを考えた食事
毎日の食事選びは、中型犬の健康を維持するために大切なポイント。
カロリーオーバーや栄養の偏りは肥満のリスクが高くなるため、日頃から栄養バランスを踏まえてフードの種類・量を考えることが大切です。
近年は特定の犬種に合わせた栄養バランスになるように作られたドッグフードもあるので、栄養バランスが不安な飼い主さんはぜひ取り入れてみましょう。
定期的な健康診断とワクチン接種
中型犬を長生きさせるためには、病気の予防が何より大切です。
特に犬は人間のように体調が悪いことを言葉で伝えられないうえ、本能的に多少の体調不良・ケガは表に出さないように隠す傾向があります。
そのため「元気そうだから大丈夫」と受診せずに放置してしまい、病気やケガが悪化してしまうことも少なくありません。
そこで大切なのが、動物病院での定期的な健康診断。
身体検査や血液検査、レントゲン検査などのさまざまな検査を受けられるので、愛犬の体に隠れた思わぬ健康リスクの早期発見につながりますよ。
健康診断の年齢・頻度については決まりがありませんが、一般的には生後6か月~6歳までは1年に1回、シニア期にあたる7歳以降は半年に1回の受診をおすすめします。
また、病気の予防において「ワクチン接種」も大切!
法律で摂取が義務付けられている狂犬病ワクチンはもちろんですが、任意で接種する混合ワクチンも1年に1回接種することが望ましいです。
犬パルボウイルス感染症や犬ジステンパーウイルス感染症など、愛犬がかかる可能性がある感染症にはさまざまな種類があります。
なかには致死率が高いものもあることから、ワクチンを通して予防することも愛犬が健康的に長生きできるようにするためのポイントです。
愛犬が長生きできるように、適切なサポートをしてあげましょう!

出典:https://www.shutterstock.com
愛犬だけに限らず、全ての生き物において寿命は避けられないもの。
しかし、普段の食生活や病気の予防といった、普段の生活でできる小さなサポートを心掛けることで、愛犬の寿命を延ばすことにつながります。
本記事で紹介した老化のサインや飼い主さんができることを参考にしながら、愛犬が長生きできるようにサポートをしてあげてくださいね。
・一般社団法人ペットフード協会「全国犬猫飼育実態調査」(参照日:2025/9/26)
https://petfood.or.jp/data-chart/
https://petfood.or.jp/pdf/data/2024/3.pdf
・アニコムグループ『家庭どうぶつ白書』(参照日:2025/9/26)
https://www.anicom-page.com/hakusho/
https://www.anicom-page.com/hakusho/book/pdf/book_202412_2_5.pdf
https://www.anicom-page.com/hakusho/book/pdf/book_202412_2_2_1.pdf
著者情報
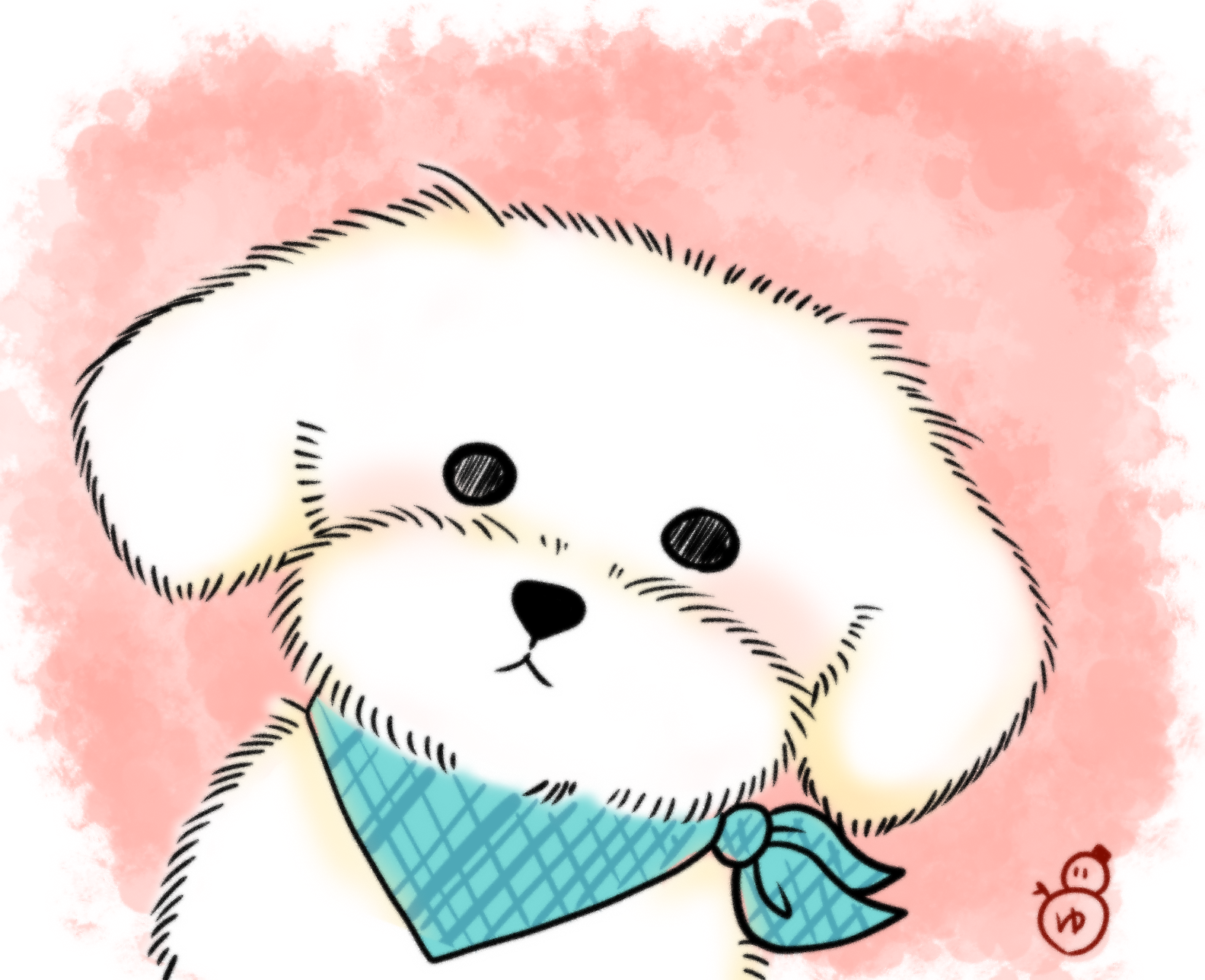
西野由樹
生粋の犬好きなフリーランスWebライター。執筆のお供はコーヒーと愛犬のマルチーズ「こたろう」。
やんちゃな愛犬にちょっかいを出されつつ、今日も実体験・調査に基づいた執筆で、読んで楽しい記事づくりに勤しむ。