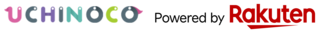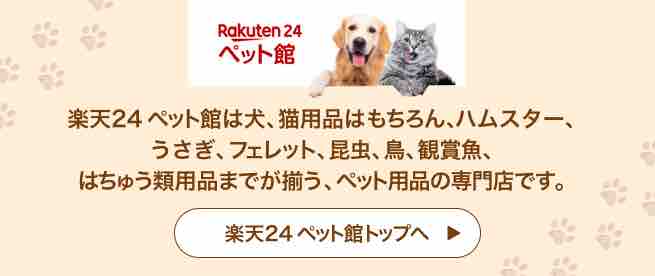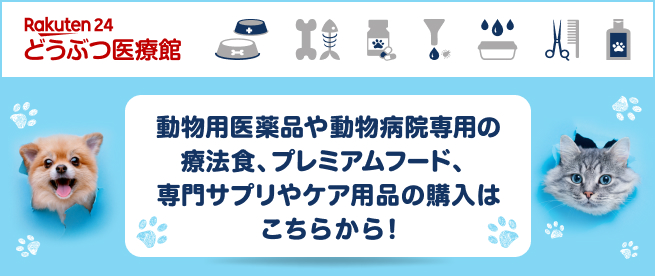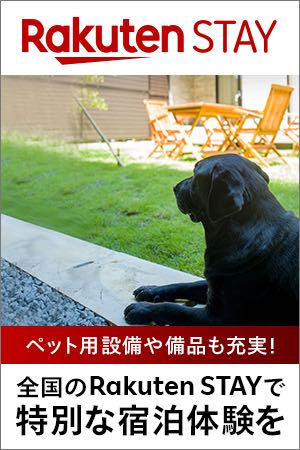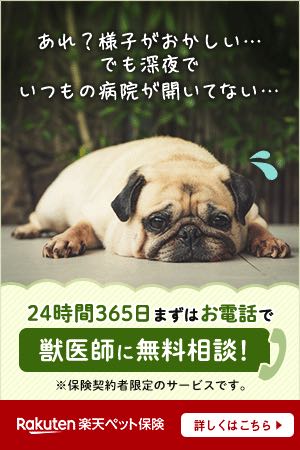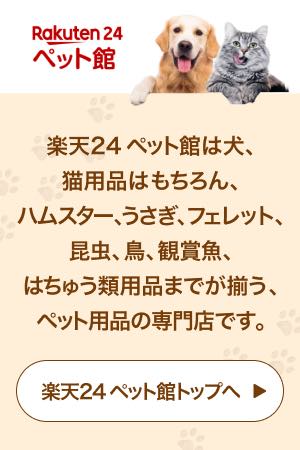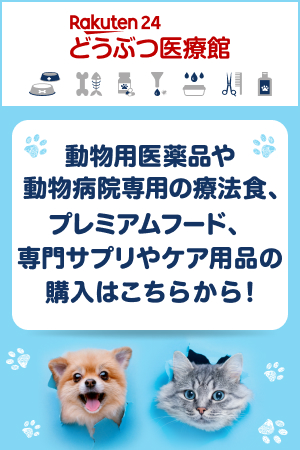普段はおとなしい愛猫が鳴きやまないとき、それは何らかの強い要求や不満があるサインです。飼い主として、何ができるのでしょうか?愛猫が鳴きやまない理由をまとめてみましょう。
猫が鳴きやまない理由とは?

出典:https://www.shutterstock.com
愛犬の無駄吠えについてはよく聞きますが、愛猫が鳴きやまない時はどのような場合かと言いますと、よく見かけるのは子猫が鳴きながら歩いている時や、飼い主に向かってきーきーと鳴き声をしつこく上げている時です。子猫はいっぱい御世話をして欲しくてお母さん猫を何度も呼びます。
これらの鳴き声は無駄に聞こえるかもしれませんが、実際には遊んで欲しい時や構って欲しい時、そしてごはんをおねだりしている時です。しかし、ついかわいいからと甘やかしてしまいがちです。しかし、子猫のうちにあまり言うことを聞きすぎるのは飼い主の姿勢としては望ましくありません。
ある程度は無視しても問題ありません。鳴いても何かを要求すれば聞いてもらえると思い込ませてしまうと、後々大変になることがあります。鳴いても無駄だと理解させることが重要です。少なくとも叱ったり怒鳴ったりするよりは良い方法です。
では、大人になってから鳴きやまない時はどうでしょうか?もちろん、ごはんを欲しがる時や甘えたい時にも鳴くことがありますが、不満や要求がある時も頻繁に鳴くことがあります。発情した時や病気の時も鳴き声が増えますから、状況を見極めることが重要です。しぐさと組み合わせて観察すると、愛猫の気持ちを理解しやすくなるでしょう。猫は自己表現が豊かな動物で、鳴き声を巧みに使い分けて自己主張します。鳴き声のパターンを覚えることで、愛猫の気持ちを察する手助けとなるでしょう。こういった特性が、長い間人間の友として愛されてきた理由かもしれません。
「ニャーニャー」と高い声で泣き続けている時

出典:https://www.shutterstock.com
「ニャーニャー」と高い声で泣き続けている時、その気持ちとして考えられるものは、一番わかりやすいのはごはんを欲しがっている時です。中には体をよじ登ってくる子もいますが、お皿を出すまで大人しく待たせてあげましょう。子猫はいつもお腹がすいているので、しつこく鳴いてきます。成猫でも要求が通らないとずっと鳴いていることがあります。
ドアを開けてほしい、お風呂で濡れたくない、何かを取ってほしいなど、要求が通らないときも、ずっと鳴いています。明らかに母猫が飼い主だと分かる場合は無視が効果的ですが、そうでない場合は適切に応じてあげると収まります。
また、病気の時や発情期にもよく鳴きます。特に発情している場合、夜中に鳴かれると近所迷惑になり、飼い主も寝不足になります。基本的には様々な状況を考えて、避妊・去勢手術を検討することをおすすめします。病気かどうかは様子を見ながら判断する必要がありますが、急に体重が減少したり、くしゃみを繰り返したり、不調な行動が見られた場合は、早急に獣医師の診察を受けるべきです。
「グルル」と喉を鳴らしている時

出典:https://www.shutterstock.com
猫は喉を「グルル」と鳴らして鳴くこともよくあります。これは一般的に喜んでいるときの表現です。例えば、頭を撫でてあげたり、一緒に遊んであげたりすると、よくこのように鳴きます。
「ンー」と鳴く時
ほとんど口を開けず、「ンー」と鳴き続けている時には、2つのケースが考えられます。どちらかを判断するのは、鳴き声の高さで比較的簡単です。
低い音の場合、それは威嚇のサインであることが明らかですので、手を近づけるのは避けましょう。
高い音で鳴いている場合、それは飼い主の注意を引こうとしているか、甘えたいときです。頭を出して寄ってきたら、撫でてほしいサインですので、優しく撫でてあげてください。
体調不良の時

出典:https://www.shutterstock.com
猫が鳴きやまない時は、甘えや要求だけでなく、体調不良やケガなどを飼い主に伝えていることもあります。猫は具合が悪かったり弱っていたりする時、それを悟られないように隠す習性があります。これは野生の動物共通の習性とみられ、天敵などから身を守るためと考えられます。
飼い猫の場合、飼い主に守られ、餌をもらい、要求に応えてもらったり甘えたりして、心を許しているため、具合が悪い時には鳴いて飼い主に助けを求めていることもあるのでしょう。
猫の鳴き声が明らかに普段と異なる時、例えば、かすれていたり、唸るような鳴き声であったり、絞り出すような声であったりする場合は、体調不良の可能性があります。風邪の場合にはくしゃみや鼻水や目やにや食欲不振などの症状も伴います。明らかに普段と違う様子であれば、時獣医師に診てもらいましょう。
認知症の場合
猫が高齢になると、人間と同じように認知症の症状が出ることもあります。夜中に鳴き続けて昼夜が逆転したり、徘徊したり、攻撃的になったり、性格が変わってしまう場合もあるのです。
また、猫が鳴き続ける時には、それ以外にも重篤な病気が隠れていることもあります。特にシニア期に特有の病気もありますので、普段と違う鳴き声・行動が見られる時は、その様子をよく観察し、獣医師に伝えましょう。
鳴き方から猫の気持ちを早めに察してあげよう

出典:https://www.shutterstock.com
猫が飼い主に向かって鳴くのは、それが唯一のコミュニケーション手段だからです。猫にとって頼りになるのは飼い主さんだけです。猫の気持ちを素早く感じ取ってしっかりと対処すれば、鳴き続ける問題は解決するでしょう。鳴き声だけでなく、仕草、行動なども注意深く観察することは、猫の気持ちを理解するのに役立ちます。
著者情報

UCHINOCO編集部
UCHINOCO編集部では、ペットに関するお役立ち情報をお届けしています。