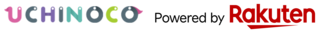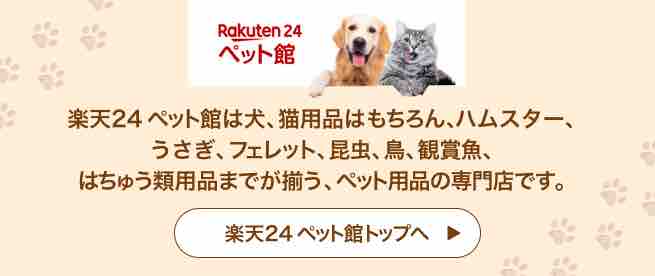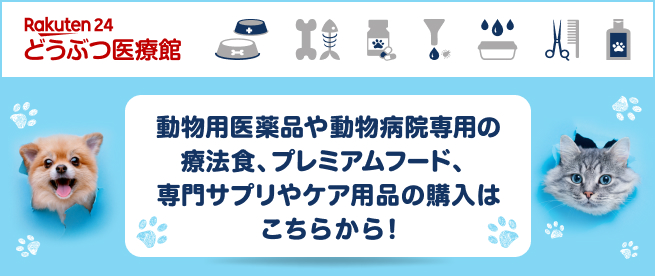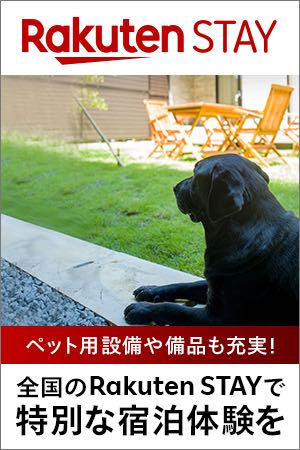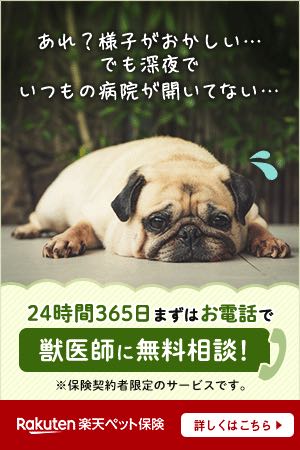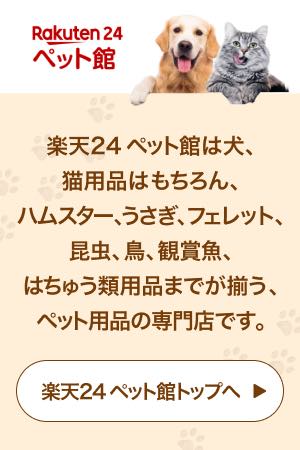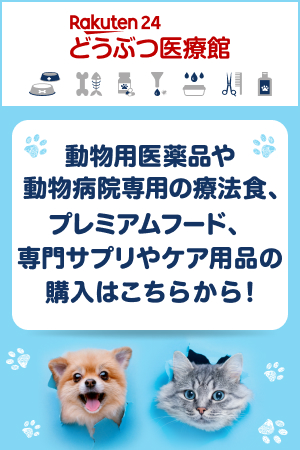犬の貧血の症状

出典:https://www.shutterstock.com/
まずは、犬の貧血の症状についてご説明します。
症状を知っておけば、犬に異常が起こったときにも正しい対処ができるでしょう。
歯茎が白っぽくなる
犬の貧血の症状として挙げられるのは、歯茎が白っぽくなることです。
健康な犬の歯茎はピンク色をしていますが、貧血気味の犬の歯茎や舌は白っぽくなります。
ちなみに、血尿や黄疸がみられたときは、貧血ではない病気を疑う必要があるでしょう。
足元がふらつく
人間と同様に、犬も貧血を起こすと足元がふらつきます。
場合によっては、歩いているときにへたりと座り込んでしまうこともあるでしょう。
また、疲れやすくなるため、散歩をするのを嫌がるようになります。
いつもより寝る時間が多ければ、貧血の可能性も考えられるでしょう。
犬が貧血を起こすと、寝ているときの立ち上がりも遅くなります。
食欲不振
犬が貧血を起こすと、当然ながら元気がなくなります。
また、食欲不振もみられるため、食事の際にご飯を食べ進めないときは貧血を疑う必要があるかもしれません。
寒がる
貧血の症状として、体温調節が難しくなるという点が挙げられます。
特に体温を上げることが難しくなるため、犬は寒がるようになるでしょう。
エアコンやヒーターなどの温度設定は普段通りなのにも関わらず犬が寒がるときは、貧血の可能性もあります。
犬の貧血の原因

出典:https://www.shutterstock.com/
次に、犬の貧血の原因を解説します。
犬が貧血を起こさないように、日頃からできる限りの対策をすることが大切です。
食べ物による中毒
犬に与えてはいけない食べ物として有名なネギ類には、アリルプロピルジスルファイドという成分が含まれています。
アリルプロピルジスルファイドは犬の赤血球を溶血してしまうため、赤血球が不足して貧血を起こします。
ネギ類には、長ネギや玉ねぎはもちろん、ニラやにんにくにも含まれるため、注意が必要です。
アリルプロピルジスルファイドによる中毒は、重度になると命に関わることもあります。
寄生虫感染
犬は、マダニの吸血により犬バベシア病を発症することがあります。
犬バベシア病は、赤血球を破壊しながら増殖するため、食べ物による中毒と同様に貧血を起こしてしまうでしょう。
当然ながら、犬バベシア病による貧血も命に関わることがあり、注意しなければなりません。
外傷・生理
貧血は、体内から多くの血が流出することで発症します。
そのため、犬同士の喧嘩や交通事故などによる外傷や、メス犬の生理によるものでも貧血を起こすでしょう。
病気
犬の貧血は、重度の病気のサインとなることもあります。
骨髄系の病気である白血病や、免疫機能に異常が現れる免疫介在性溶血性貧血など、放置しておくと命に関わる可能性のある病気なので、犬に貧血の症状がみられたときには、早めに対処しなければなりません。
貧血を起こしやすい犬種
犬種によっては、貧血を起こしやすいといわれています。
もちろん個体差はありますが、シーズーやプードル、マルチーズやコリーなどは、ほかの犬種に比べると貧血を起こしやすいと考えられます。
また、性別でいうとオス犬よりもメス犬のほうが生理があるからか、貧血を起こしやすいでしょう。
犬の貧血の対処方法

出典:https://www.shutterstock.com/
最後に、犬の貧血の対処方法をご紹介します。
貧血は命に関わることもあるため、しっかりと対処しなければなりません。
犬の意識・呼吸の確認
まずは、犬の意識があるかを確認しましょう。
犬の名前を呼んでみて、表情が変わったり尻尾を振ったりするか、反応を確かめます。
また、犬の名前を呼んだ際に反応がなくとも、身体をゆすったり押したりしてはいけません。
意識が朦朧としている犬は、パニックになって攻撃的になる可能性もあります。
犬の意識があることを確認したら、呼吸をしやすい姿勢にしてあげましょう。
首や頭を伸ばしてあげることで、犬は呼吸が楽になるはずです。
動物病院へ連れて行く
犬の貧血は、場合によっては命に関わることもあるため、なるべく早めに動物病院へ連れてことをおすすめします。
一時的な症状であったとしても、放置しておくと何度も貧血を起こすこともあるでしょう。
そうなると犬の身体に負担がかかることはもちろん、病気に気が付くのも遅くなってしまいます。
獣医師に診せることで原因を特定できますし、正しい治療を行うことができるはずです。
ちなみに、獣医師がスムーズに診察できるように、犬が貧血を起こした際の呼吸の仕方を確認しておきましょう。
呼吸が荒いか、呼吸音に違和感がなかったかなど、少しでも気になる点があれば獣医師に伝えることが大切です。
犬の貧血の対策方法
犬の貧血は、ある程度の対策をすることができます。
まずは、毎日栄養バランスの取れた食事をさせることです。
健康的な身体を維持するための動物性たんぱく質や脂質、ビタミンやミネラルなど、総合栄養食の基準を満たしたドッグフードを適量与えるようにしましょう。
また、適度な運動も効果的です。もちろん個体差や年齢によって運動量は異なりますが、定期的にドッグランや広い公園などで思い切り運動をさせることで、運動不足やストレス解消に繋がるでしょう。
犬の貧血に気を付けよう

出典:https://www.shutterstock.com/
犬は、食べ物による中毒や寄生虫感染、怪我などによる外傷などで貧血を起こします。
貧血は足元がふらついて歩けなくなるほか、食欲不振で元気がなくなることもあるでしょう。
対処方法として間違いないのは、やはり動物病院へ連れて行くことです。
獣医師に診せることで犬の貧血の原因を特定できますし、正しい治療を行うことができるでしょう。
著者情報

けんぴ
若い頃はドッグトレーナーとして、警察犬の訓練やドッグスポーツなどを行う。
それらの経験を活かし、ペット系ライターとして活動中。
現在はすっかり猫派となる。
好きな犬種・猫種はボーダーコリーとノルウェージャンフォレストキャット。