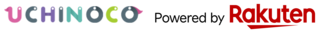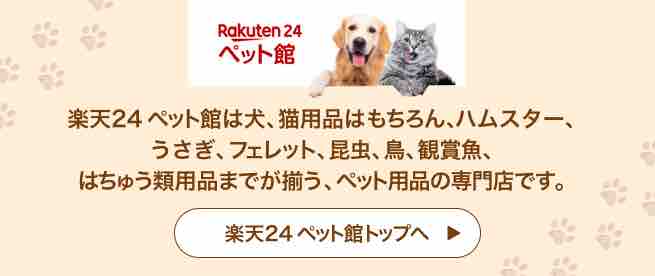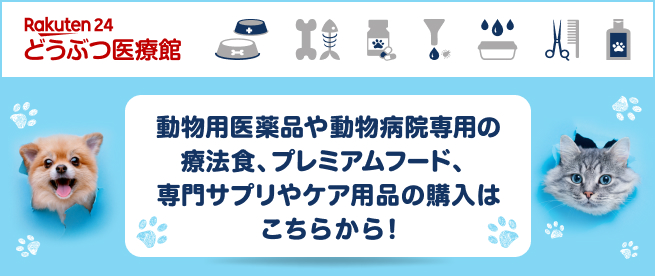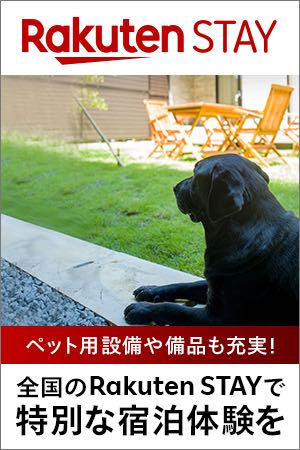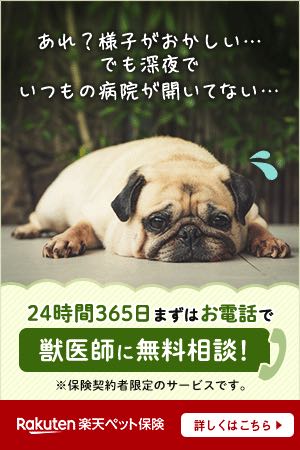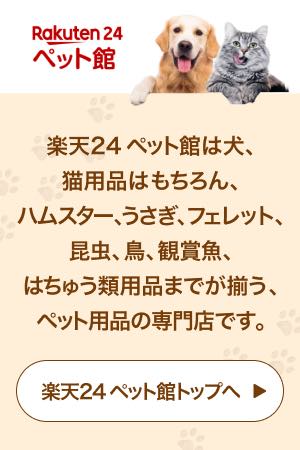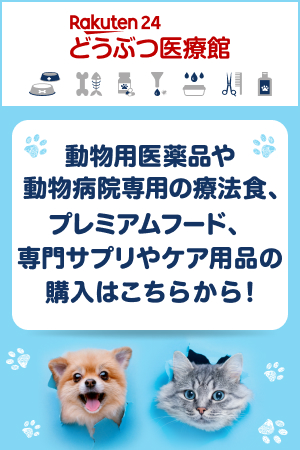猫を飼う前に確認すること
猫に限らず、ペットをお迎えするということは、その動物に対しての責任を最期まで負うことだということを、肝に銘じておかなければなりません。猫も人間と同じように、それぞれ性格が異なり、病気になることもあります。どんな状態であれ、ひとつの命を守る覚悟が必要です。
もし、これから猫をお迎えしたいと思っているのであれば、以下の内容について考えてみましょう。
・猫を飼える住宅や環境ですか?
・猫を迎えることに家族全員が合意していますか?
・動物アレルギーの心配はありませんか?
・寿命まで変わらぬ愛情と責任をもって飼育する覚悟はありますか?
・世話をする体力と時間はありますか?
・高齢になった猫を介護する心構えはありますか?
・経済的負担は考慮できていますか?
・猫へのしつけや、万が一猫が外に出てしまい、近隣の方々にご迷惑をおかけした場合、
責任を取る覚悟はありますか?
・ライフステージが変わった際も継続飼養する覚悟がありますか?
・万が一飼えなくなってしまったときのことを考えていますか?
これらの質問に、すべて自信をもって「はい」と言えるようになってから、お迎えをするようにしましょう。
猫の命を守るためには、たくさんの覚悟と準備が必要です。自分が最期までちゃんと責任をとれるのか、しっかりと考えてからお迎えしましょう。
猫を飼う前の準備

出典:https://www.shutterstock.com/
猫を迎える前の準備として、必要なものを揃えたり、安全な環境を確保したりと、意外とやるべきことはたくさんあります。具体的に見ていきましょう。
住環境を整える
猫が家の中で安全に過ごすために、以下のポイントを意識して住環境を整えましょう。
誤食の危険があるものは置かない
ひも、ビニール、小さなもの、毛、羽のついたおもちゃなど、猫が興味をもち噛んでしまうものはたくさんあります。できるだけ家の中は整理して、誤食の可能性があるものは、猫が取り出せない場所にしまっておきましょう。生ゴミについても、こまめに処理をして猫の口に入らないように気を付けましょう。
家具の隙間は塞いでおく
猫は、狭くて暗い場所が大好きで、好奇心もあり、家具の隙間や裏側といった場所に入ってしまうことがあります。特に、初めての場所では警戒心もあり、狭い場所から出てこなくなることも。引っ張り出せないような狭い隙間は、あらかじめ塞いでおきましょう。
コード類のカバーをする
猫の中には、電気コード類を噛んでしまう子もいます。感電の恐れもあり、コード類をそのままにしておくのは危険です。カバーをつけるなどの工夫をして、対処しましょう。
キッチンやお風呂場に入れないようにしておく
火の元や刃物があるキッチン、溺れる可能性があるお風呂場といった場所は、入れないように柵を設けるなどの対応が必要かもしれません。お風呂は必ず猫がいないことを確認して扉を閉めるなど、日頃から気を付けておくと良いでしょう。
脱走防止の工夫をする
網戸はストッパーを取り付けて固定する、玄関のドアはペット用のフェンスを設置するなどして、うっかり外に猫が飛び出してしまわないように対策するのも重要です。
床掃除の洗剤使用を控える
床掃除はスプレーなどの洗剤を使用することが多いかと思いますが、これらの洗剤を使用した床を猫が誤って舐めてしまった場合、嘔吐下痢などの症状を引き起こしてしまう可能性があります。したがって、洗剤の使用は控えて、水拭きで完結するようにしましょう。
猫との暮らしに必要なアイテム
猫をお迎えする前に、必要なものを揃えておく必要もあります。以下のものは、必ず使うこととなるため、事前に購入しておきましょう。
・猫トイレ、猫砂
・キャットフード
・猫用食器
・爪とぎ
・ケージ
・寝床用クッション、ドーム等
・爪切り、ブラシ、歯磨きアイテム
・消臭剤
お迎えする猫の年齢や体格によって、適したサイズが異なるものもあります。また、キャットフードについても、年齢に応じたものを選ぶようにしましょう。
かかりつけの動物病院を探しておく
猫が体調を崩した時に、すぐに診てもらえるようにかかりつけの病院を探しておきましょう。診療日や診療時間もチェックし、念のために、地域にある動物病院の情報を複数確認しておくと休診日の時なども安心です。
うちのこ初日(お迎え当日)

出典:https://www.shutterstock.com/
猫をお迎えした当日は、可愛くて遊びたい気持ちでいっぱいになるかもしれません。しかし、新しい環境に猫が慣れることを優先してあげましょう。猫から近づいて甘えてこない限りは、少し離れたところで優しく見守り、あまり構いすぎないことが大切です。
猫は、よく眠る動物であることも理解してあげましょう。眠っているところを急に触ったり、大きな声や音で驚かせて邪魔をすることがないように、注意する必要があります。
また夜行性である猫は、夜間に動き回ることも考えられます。したがって、人間が眠る前に危険な箇所がないかを必ず確認してから眠るようにしましょう。
猫のトイレ
猫は、もともと砂の上で排泄をする習性があるため、基本的にトイレをしつける必要はありません。お迎えした当日からトイレで問題なく排泄できる子もたくさんいます。しかし、環境の変化によって戸惑うこともあるため、お迎えするまでに他の場所で飼われていた場合はその猫自身の排泄臭のついたトイレ砂をもらって、新しく設置するトイレの砂に混ぜておくと良いでしょう。
猫がトイレ以外の場所で排泄してしまう場合は、いくつかの原因が考えられますが、トイレの砂の種類やトイレの形状・設置場所を変えるだけで改善することもあるため、猫の好みを探ってあげることも大切です。
トイレが汚れていると、排泄を我慢してしまうこともあります。できるだけ早く排泄物を掃除して、いつも清潔な状態が保てるよう心がけましょう。トイレをしている最中は近づかず、安心して排泄できる環境を整えることも大事です。
猫のごはん・おやつ

出典:https://www.shutterstock.com/
猫のごはんやおやつは、人間が食べるものと同じというわけにはいきません。具体的に、どのような点に注意すれば良いのか解説します。
猫のごはん
猫のごはんは、月齢・年齢に応じたものを選びましょう。特に、子猫の時期は食べられるフードが細かく変わってくるため、十分な確認が必要です。基本的に、生後3~4週間まではミルクのみを与えます。頻度は、生後1週間までは2~3時間、生後1~2週間までは4時間おき、生後3週間から1か月までは6時間おきに与えます。
生後4週間を過ぎて乳歯が生え始めたら、徐々に子猫用のウェットフード等へと変えていきます。月齢に応じた適正量をよく確認し、1日3回程度に分けて与えます。その後は、猫が1日に必要とする栄養をバランスよく含んだ総合栄養食に移行すると良いでしょう。
猫のフードを手作りするという方法もありますが、手作りでは栄養の偏りが生じやすく、食べられる食材とそうでない食材をきちんと理解しておく必要があり、なかなか大変です。もし、猫にとって有害な食材を口にした場合、食中毒やアレルギー症状、命の危険につながるリスクもあります。
猫のおやつ
猫のおやつは、飼い主さんとのコミュニケーションや毎日の楽しみのために上手に活用しましょう。喜ぶからといって与えすぎてしまうと、肥満の原因になってしまいます。総合栄養食を適正量食べていれば、おやつまで与える必要はありませんが、飼い主さんとの楽しい時間を作ることは、猫にとっても喜ばしいことでしょう。量に気を付けて、上手に活用することをおすすめします。
猫のワクチン接種
猫のワクチン接種は、伝染病の予防や重症化防止につながり、健康を守るために欠かすことができません。
一般的に、子猫の場合は生後2ヶ月と生後3ヶ月のタイミングで混合ワクチンを接種します。その後は、年1回のペースで追加接種をしていくこととなります。ワクチン接種のタイミングは動物病院によっても多少異なるため、かかりつけの病院で相談し、勧められるタイミングで受けましょう。
猫のお手入れ

出典:https://www.shutterstock.com/
猫のお手入れには、どのようなものがあるのでしょうか。内容や頻度、ポイントを簡単にご紹介します。
ブラッシング
猫は自分で毛繕いをする習性があり、抜け毛が多いと毛玉を飲み込んで健康を損ねる原因にもなります。毛が生え変わる換毛期には、短毛種なら2~3日に1回、長毛種なら毎日、5分程度を目安に行いましょう。
シャンプー
猫は、毛繕いによって体を清潔に保っています。そのため、基本的にはシャンプーの必要はありません。しかし、長毛種であれば、被毛のベタつきやフケが出てくるため、1ヶ月~数ヵ月に1回のペースでシャンプーしてあげると良いでしょう。換毛期のタイミングで毛玉の嘔吐が多い場合は、この限りではありません。なお、シャンプーの際は、必ず猫用の製品を使ってあげましょう。
歯磨き
歯磨きは、嫌がる子の多いケアの1つですが、歯石になる前にこまめにお手入れしてあげる必要があります。頻度としては1週間に1回以上、まずはほんの短時間だけガーゼで磨くなど、負担の少ない方法で試してみましょう。どうしても、直接歯磨きをすることが難しいのであれば、歯磨き効果が期待できるおやつや、ガーゼなどで歯を磨くことも1つの方法です。
爪切り
猫の爪切りを怠ると、とがりすぎた爪が家具などにひっかかり、宙吊りになったり爪が剥がれるなどのケガを負うリスクがあり危険です。また、自身で痒い場所をかいたとき、皮膚を傷つけてしまう恐れも。最低でも、3週間から月に1回は爪切りをしましょう。嫌がる子は、何日かに分けて切るのもおすすめです。
顔まわりのケア
少量のカサカサとした目やにが気になる時は、清潔なコットンでそっと取り除きましょう。涙があふれやすい猫種の場合も同様です。耳は、赤みやニオイがなければ特にお手入れは必要ありませんが、折れている耳を持つ猫は、汚れがたまり過ぎない程度に柔らかいペット用ウェットティッシュなどで優しく拭く程度のお手入れをしてあげるのも良いでしょう。顎は、フードのかす等で汚れやすいため、水に濡らしたコットンなどで拭き取って綺麗な状態を保ってあげてください。
猫の避妊・去勢手術
猫の避妊・去勢手術については、飼い主さんがメリットとデメリットをよく考慮して決めていくべき問題です。避妊・去勢手術についてはさまざまな考え方がありますが、最近は望まない出産を避けるだけでなく、一部の病気の予防につながるという理由などで、避妊・去勢手術を勧めるケースも多いようです。猫の今後のことを考えて、避妊・去勢手術を受けるかどうか考えていきましょう。
猫とのコミュニケーション

出典:https://www.shutterstock.com/
ここからは、猫が喜ぶ遊びや、触り方のコツをご紹介していきます。
おもちゃで遊ぶ
性格や年齢にもよりますが、猫は基本的に遊ぶことが好きです。家の中で暮らす猫は、どうしても運動不足になりやすいため、肥満防止やストレス発散のためにもおもちゃを使った遊びを取り入れてあげましょう。
特に、獲物に見立てたおもちゃを追いかけて捕まえる遊びは、猫の狩猟本能を刺激し、夢中になる子が多いです。小さなぬいぐるみやヒモのついたおもちゃは、とても人気がありますが、猫が飲み込んでしまわないように注意しましょう。
スキンシップ
猫がスキンシップを好むかどうかは、性格により違ってきます。いつも飼い主さんに触れられていたいような甘えん坊もいれば、ほんの短時間だけ甘えたい時に甘えてくる子もいます。
また、どこを触ったら喜ぶのかについても、好みが分かれやすいところです。一般的には、頬やあご下、耳の後ろあたりに触れると気持ち良さそうにする子が多いです。
逆に、前足の先やお腹、尻尾、腰あたりは、嫌がる子が多いとされています。急所や感覚器官が敏感な場所は、猫同士でも毛繕いをしない場所であり、こうした場所は避けた方が無難でしょう。
猫のお留守番
基本的に、猫は単独行動をとる動物です。健康な成猫であれば1日くらいのお留守番はできます。しかし、飼い主が不在の間は、安全に過ごせるように環境をしっかり整えましょう。
まずは、温度管理です。エアコンを使って快適な室温に設定し、仕事などで朝から晩まで留守にする時などはタイマーではなくつけっぱなしにしておきましょう。また、猫が自分で温度管理できるように、冷感アイテムとあったかいブランケット等のアイテムの両方を備えておくのが望ましいです。
誤食につながるようなものは引き出しの中などにしまい、落として壊れるものは置かないなどの配慮も必要です。
お水やフードについては、外出頻度が多く時間も長めであれば、自動給餌器の使用も検討した方が良いかもしれません。
猫のペット保険
猫も人間と同じように、病気や怪我で治療を必要とする場面が出てくる可能性があります。人間の場合は、公的な医療保険制度で出費を抑えることができますが、猫の場合は公的な保険がありません。
そのため、動物病院での治療は自由診療となり、想像よりも高額な費用がかかります。
ペット保険は、ペットのための保険です。病気や怪我で動物病院にかかった時、診療費の一部は保険金として補償されます。人間の医療保険に近いイメージになります。治療費が高額になるかもしれないと不安になり、受診を躊躇しなくて済むでしょう。いざという時のために、加入しておくと安心です。
災害時の備え

出典:https://www.shutterstock.com/
大雨や地震などで避難しなければならない時、猫も一緒に安全な場所へ速やかに移動でき、避難先でもできる限り快適に過ごせるよう備えておくことは非常に重要です。
猫用の防災グッズをまとめておく
災害時には、すぐに猫を連れて避難できるように、以下の防災グッズをまとめておきましょう。
・(処方されていれば)薬
・連絡先入りの首輪
・キャリーバッグ、もしくはケージ
・ハーネス、リード
・ペットシーツ、猫砂、汚物処理袋
・5日分の小分けにしたフード、おやつ、食器、水
・おもちゃ
・ペット用ウェットシート
その他にも、使い捨ての手袋や新聞紙、食品用ラップ、タオル、ビニール袋、洗濯ネットなどがあると便利です。
マイクロチップ、迷子札
災害時、ペットとはぐれて迷子にさせてしまうケースは珍しくありません。特に猫の場合、基本的には自宅以外の場所で過ごすことに慣れていない子が大半で、避難先で脱走されてしまうと探すことが困難です。
マイクロチップの装着や、連絡先の書かれた首輪の装着は、飼い主さんが猫にしてあげられる対策のなかで、とても重要なものです。首輪は、ひっかかって首が絞まらないように負荷がかかると外れるセーフティタイプのものがおすすめです。しかし、外れてしまうと保護されたとしても飼い主の名前が分からないため、マイクロチップも装着しておく方が良いとされています。
マイクロチップは、個体識別番号が記録された小さな円筒型のもので、首の後ろに専用の注射器で埋め込みます。装着後は、日本獣医師会などに登録の手続きを行い、いざという時は飼い主の情報と照合することができます。
指定避難場所の確認
いざという時に慌てないために、近隣の避難場所を確認し、猫も一緒に避難できる場所を把握しておきましょう。そして、避難場所までの移動や避難所ではぐれてしまわないように、首輪と迷子札をつけ、キャリーバッグに入れて運びましょう。日頃から、迷子札のついた首輪や、連絡先の記載された首輪を装着していると、家から脱走した時の備えにもなります。
避難訓練をしておく
災害時は、1秒でも早く安全な場所に避難することが大事です。必要なアイテムはすぐに出せるようにまとめておき、実際に避難する時を想定して訓練しておきましょう。
まとめ
猫との暮らしは、実際に一緒に暮らしてみないと分からないような、幸せな時間をたくさんもたらしてくれます。一方で、大事な命を守るという覚悟や、病気や怪我、老衰など、猫の一生で起こってくるさまざまな出来事から逃げないという強い意思・行動力が不可欠です。猫が一生幸せに暮らせるように、必要な準備と心構えをして、お迎えしてあげてくださいね。