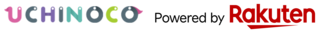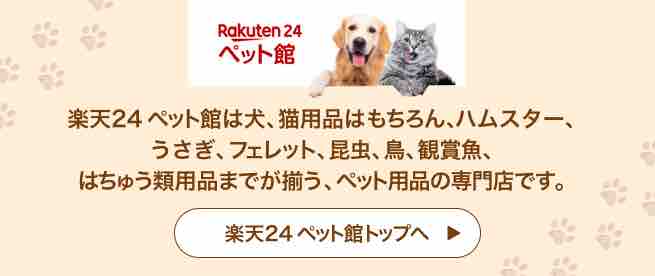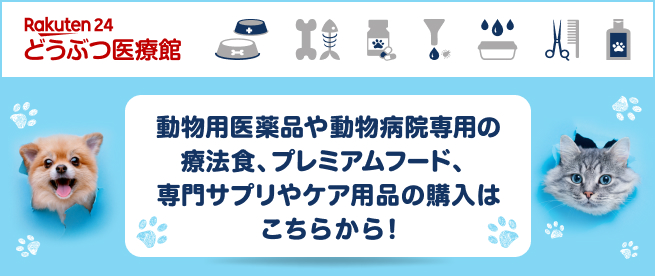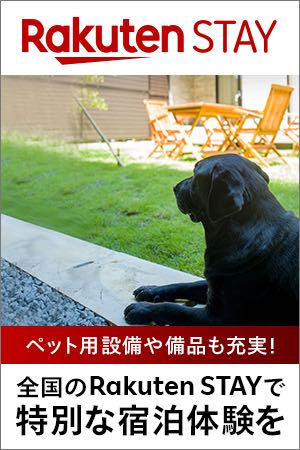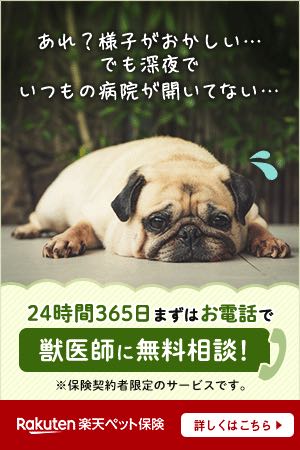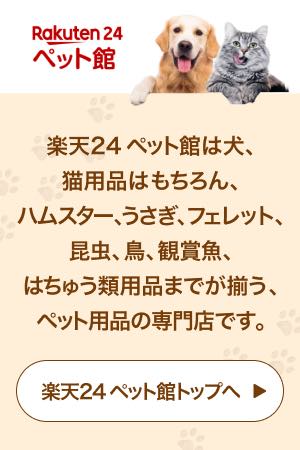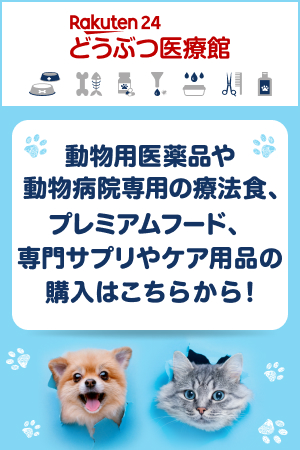寒さに弱いインコの体を守るためにできること

https://www.shutterstock/.com
室内で飼育されているインコは自分では寒さ対策ができません。気温の変化や室温の変化には体がついて行かず体調を崩しやすいということは、多くの飼い主さんの悩みの種です。インコが快適と感じる温度を飼い主さんが知っておくことで、体調不良うを引き起こす前に対処できます。年齢層によっても、インコの適温はちがってきます。ここだけはメモを取って今のインコの年齢に見合う適温を把握しておいてください。
〇1年未満の幼鳥・・25度~30度前後
〇ヒナ、長老のインコ、病気をしているインコ・・28度~32度前後
〇元気なインコ・・20度~25度
が基本的な適温と言われています。この温度をきちんと守るために、インコが生活をする鳥かごの前に温度計を置いて日々、測定するほどの気配りが必要になります。や過保護か?と思えるほどにきちんとお世話をすることが冬の寒さ対策の一環なのです
インコの寒さ対策の具体例は?
必ずペットヒーターを設置します。そしてバスタオルで鳥かごの周りを覆います。祖鳥かごまで保温できるようにその横にヒーターを設置して常に温度を管理しておいてください。カイロを使った場合はどうか?というと直接ケースの中に投入すると、酸素を消費するという性質上(カイロが)危険ですので使えないことを知っておいてください。急に保温をしなければ行けないばあいにはケースの外側から貼り付けるようにしてください。絶対にインコに直接触れるような扱い方はしないでください。
インコが元気に冬を越すための方法は?

https://www.shutterstock/.com
秋口になると急に気温が下がりはじめます。インコも寒さを感じ始める時期でもあるので、早めの保温準備が必要になります。体が小さい分、自分で体温を維持できない場合が多いのです。まずは保温の仕方をきちんと飼い主さんが知ることで、寒さによる体調不良を未然に防ぐことができます。
インコが体を体を丸めて背中側にくちばしを入れたままじっとしているような状謡は、かなり寒がっている状態なのです。自分で必死になって熱を守ろうとしているのです。ここまでの状態になる前に、優しく保温して命を守ってあげるのが飼い主さんの役割です。
寒さは大敵であると知ること
冬を迎える時のインコの年齢にもよって、しっかりと保温しなければいけない場合もあります。若くて元気なインコでも冬は慎重に過ごさせないといけないのです。インコが寒さを感じる体の部分は
〇くちばし
〇顔まわり
なのです。だから寒さを感じると背中側に顔をうずめるのです。自分でも自分の冷える部分を保温しようとしているのです。飼い主さんとしては、この部分を理解して外側からも保温してあげるようにしてください。インコを飼育するのが初めてと言う人でも、保温の方法さえ事前に知っておけば、重篤な状態に陥ることは未然に防げるはずです。
本格的な冬が来る前に寒さ対策を

https://www.shutterstock/.com
インコは寒いと感じて半日以上もそのまま、寒さを直接感じさせてしまうと急に体調を崩し始めます。これを阻止するためにも室温には気を配りペットヒーターがいつでも使えるように準備をしておくと便利です。寒さは、免疫力を下げてしまいます。病気を招かないためにも、インコに寒い思いをさせないという心掛けが絶対に必要だと心得ておいてください。
温かい空気の中で過ごすことで、呼吸の度にその空気を体の中に循環させるのです。これがインコが自分の体を保温する唯一の方法なので、くれぐれも、室温が下がり過ぎないように気を配ることを忘れないようにしてください。
著者情報

UCHINOCO編集部
UCHINOCO編集部では、ペットに関するお役立ち情報をお届けしています。