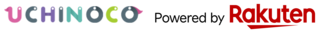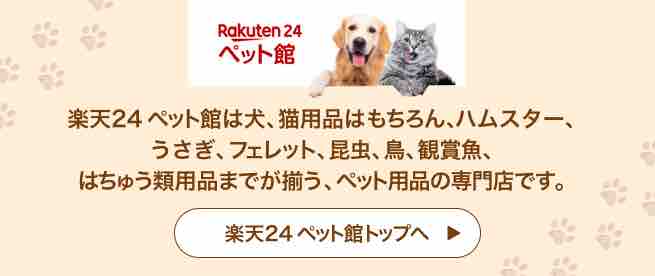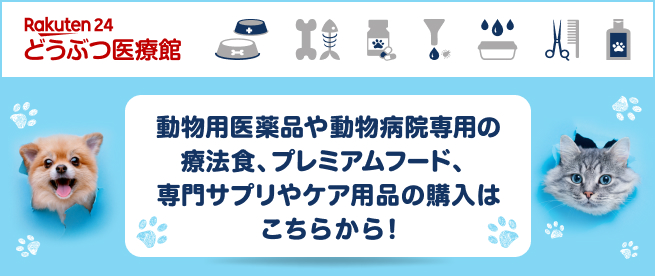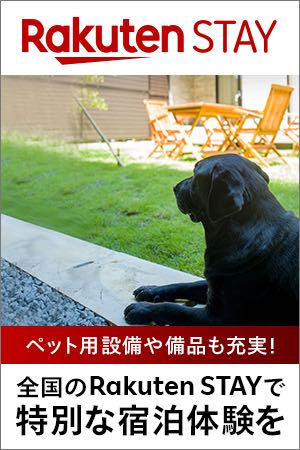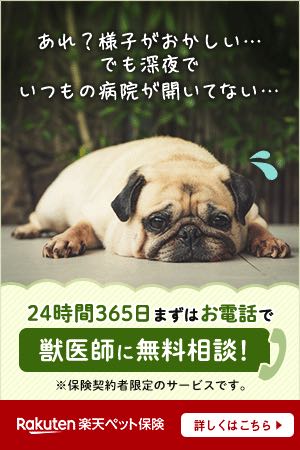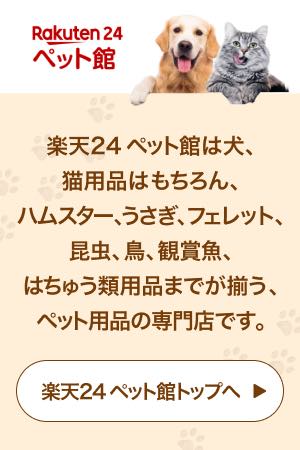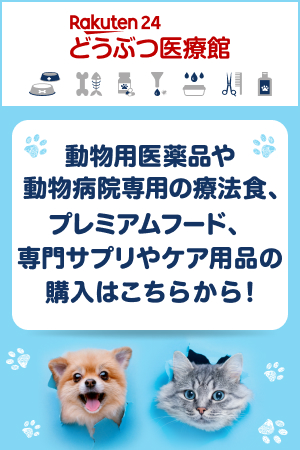捨て猫は保健所で引き取ってもらえる?

出典:https://www.shutterstock.com/
捨て猫を見つけたり捕まえたりしたら、とりあえず保健所で引き取ってもらおうと考える人は多いのではないでしょうか?
しかし、捨て猫を保健所へ連れて行ったとしても、すぐに引き取ってもらうのはかなり難しいとされています。
理由としては近年、官民一体で動物の殺処分数をできる限り減らす取り組みを進めているからです。
環境省が公開している「犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況」によると、令和5年度の猫の引取り数は25,224匹。そのうち6,899匹が殺処分されています。つまり、引取り数の約27%が殺処分されていることになります。
保健所では、捨て猫の引き取りを厳しく制限し、猫が新しい飼い主と出会えるように促すとともに、不幸な思いをする捨て猫を減らすようにしています。
捨て猫を保健所で引き取ってもらえる条件

出典:https://www.shutterstock.com/
相当な理由がない限り、捨て猫を保健所で保護してもらうのはかなり難しいです。しかし、条件によっては引き取ってもらうことは可能とされています。
環境省が公開している「犬及び猫の引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置について」によると、以下のような条件が該当する場合は、捨て猫を保健所で引き取ってもらえるでしょう。
・周辺の生活環境が損なわれる事態が生ずるおそれがあると認められる場合
・動物の健康や安全を保持するために必要と認められる場合
捨て猫が負傷・衰弱している場合などは、状況よっては引き取ってもらえる可能性があります。
しかし、保健所はあくまで最終手段であり、捨て猫が健康である場合は自分で飼育したり、譲渡先を見つけたりすることを勧められることが一般的です。
捨て猫を保健所で引き取ってもらうときの流れ

出典:https://www.shutterstock.com/
実際に捨て猫を保健所で引き取ってもらう場合、どのような手続きをすればよいか分からない人も多いでしょう。ここからは、捨て猫を保健所で引き取ってもらうときの一般的な手続きについて、流れに沿って解説していきます。
①警察署へ届出し、各自治体の保健所へ連絡する
捨て猫を拾ったら、まずは警察署へ届け出たうえで、各自治体の保健所へ連絡しましょう。
一見捨て猫のように見えても、実は飼い主がいる迷子の猫である可能性もあります。
迷子の猫の場合、もとの飼い主が警察署や地元の保健所へ届出しているかもしれません。
そのため、捨て猫を拾ってすぐに保健所へ直接持ち込むのではなく、必ず警察署へ届け出たうえで保健所へ連絡しましょう。
②捨て猫を保護するまでの経緯のヒアリング
保健所へ連絡したら、職員の方から捨て猫を保護するまでの経緯について確認されることが一般的です。
そのため、捨て猫がどこにいたのか・どのような状態なのかは保護した際にしっかり確認しておきましょう。
なお、迷子の猫である可能性も考えて、ヒアリングの際には保護した猫に関する届出がされていないかも確認しておくことをおすすめします。
③捨て猫の健康状態のチェック
保護するまでの経緯を確認されたら、捨て猫が負傷している場合などを含め、捨て猫の健康状態をチェックします。
特にケガもなく健康状態に問題がない場合は、基本的に引取りは行われません。その代わりに職員から譲渡先探しのアドバイスをされたり、自宅で飼育できないかどうかなどの相談をされたりすることが一般的です。
④飼養困難であると認められれば収容
捨て猫がケガをしている、または重度の衰弱状態である場合や、保護した人が飼養困難であると認められた場合は、保健所で引き取られます。
ケガをしている捨て猫については、保健所にて引き取られた後に適切な処置・治療を行います。
保健所で捨て猫を引き取ってもらうときの費用は?

出典:https://www.shutterstock.com/
保健所で猫を引き取ってもらう場合の費用は、都道府県によって異なります。
宮城県を例にすると、捨て猫のように飼い主不明の犬猫や負傷動物の引取りに関しては費用がかかりません。
地域によって引取手数料のルールが違う場合があるため、地元の保健所へ相談してみましょう。
ちなみに、飼養不可能になった飼い猫などを保健所で引き取ってもらう場合は、宮城県を例にすると、生後90日以下の仔猫で1匹あたり400円程度。生後91日以上の猫1匹あたり2,000円とされています。
保健所に引き取られた捨て猫はどうなるの?

出典:https://www.shutterstock.com/
保健所に引き取られた捨て猫は、まず健康状態に合わせて適切な治療が行われます。
ケガや衰弱状態が回復したら、一定の期間保健所にて保護されます。その間、捨て猫の新しい飼い主となってくれる里親を探すことが一般的です。
しかし、期間内に里親が見つからない場合、捨て猫は殺処分されてしまいます。
そのため、保健所では殺処分を避けるために、捨て猫を保護した人に対して里親探しを勧めることがほとんどです。
保健所以外に捨て猫の引き取り先を探す方法

出典:https://www.shutterstock.com/
保健所で捨て猫を引き取ってもらうのはかなり難しいこともあり、捨て猫を保護したときに引き取り先の探し方に困る人も多いでしょう。ここからは、保健所以外で捨て猫の引き取り先を探す方法を紹介します。
身近で捨て猫の里親が見つからないときにぜひ活用してみてください。
里親募集サイトでを利用する
手軽に捨て猫の飼い主を見つけるなら、インターネット上の里親募集サイトを利用してみましょう。
里親募集サイトであれば、全国にいる猫を飼いたい人が閲覧してくれるため、身近で探すより早く里親が見つかるでしょう。
また、里親候補の身分証明やコミュニケーションもインターネット上でできる点もメリットがあります。実際に捨て猫を譲渡するまでのやり取りもスムーズに進められますよ。
動物病院・ペットショップへ相談する
捨て猫の里親をより近くで見つけるなら、近隣の動物病院・ペットショップへ相談してみるのもよいでしょう。動物病院やペットショップでは公式サイトやブログなどで里親募集のページが掲載されている施設もあります。
捨て猫の健康チェックの際などに相談すれば、サイトやブログの里親募集ページへ掲載したり、里親を探してもらえたりするかもしれません。
地域の動物愛護団体へ協力を依頼する
各地域の動物愛護団体へ、里親探しの協力を依頼するのもおすすめです。
団体によっては里親募集の支援を行っていたり、シェルターにて捨て猫の一時保護をしていたりする可能性があります。犬猫の譲渡会を開催している団体も多いため、捨て猫を安全に保護しつつ、里親探しができるのがメリットです。
なお、捨て猫の一時保護を依頼する場合、団体によっては別途ワクチンの接種や不妊去勢手術にかかる費用は保護した人が負担することが一般的です。
地域の猫ボランティアへ相談する
地域の猫ボランティアへ相談してみるのも一つの手です。ボランティア団体のなかには、捨て猫の保護や譲渡支援を行っていることもあるため、捨て猫の健康状態などを伝えたうえで相談してみましょう。
動物愛護団体と同様に、各地域にて譲渡会を開催していることもあります。
譲渡会に参加することで、より多くの里親候補から捨て猫にぴったり合う飼い主に出会いやすくなるでしょう。
保健所へ連れていく前に、捨て猫の里親を探してみよう!

出典:https://www.shutterstock.com/
近年は動物愛護の観点から、保健所で捨て猫を引き取ってもらうのはかなり難しくなっています。そのため、ケガや衰弱している場合を除き、捨て猫を保護したら警察や保健所へいくのではなく、里親探しを検討してみる手段もあることも頭にいれておきましょう。
・宮城県
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/shoku-k/kainushinowakaranaineko.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/et-hc/jueki-hikitori.html
・環境省「犬及び猫の引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置について」
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/laws/nt_r02_21_4.pdf
・環境省「犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況」
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/statistics/dog-cat.html
・環境省「人と動物が幸せに暮らす社会の実現プロジェクト」
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/project/actionplan.html
著者情報
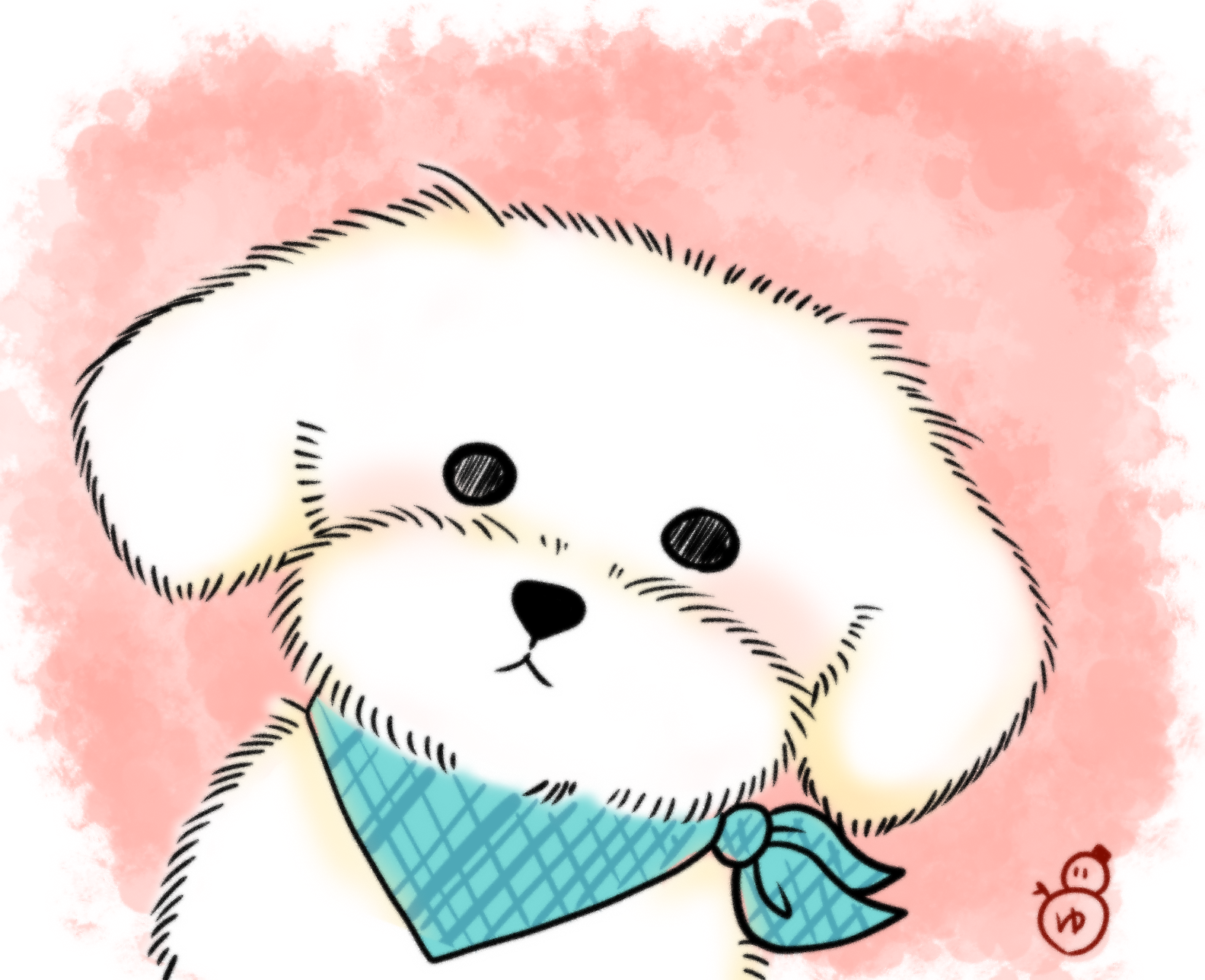
西野由樹
生粋の犬好きなフリーランスWebライター。執筆のお供はコーヒーと愛犬のマルチーズ「こたろう」。
やんちゃな愛犬にちょっかいを出されつつ、今日も実体験・調査に基づいた執筆で、読んで楽しい記事づくりに勤しむ。