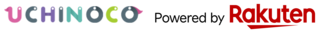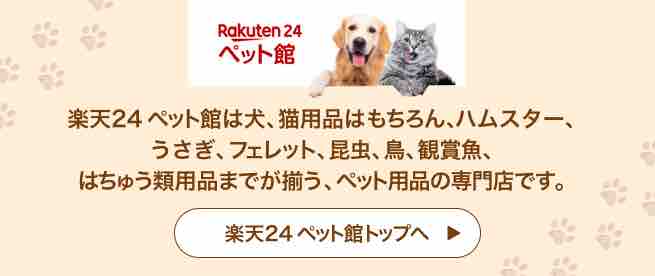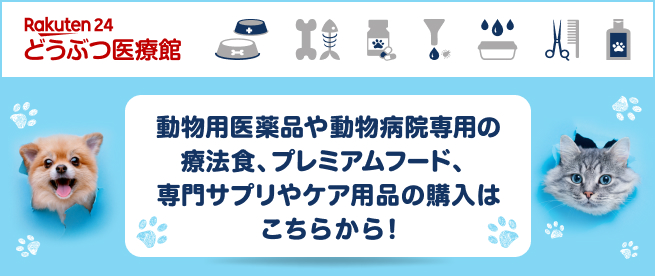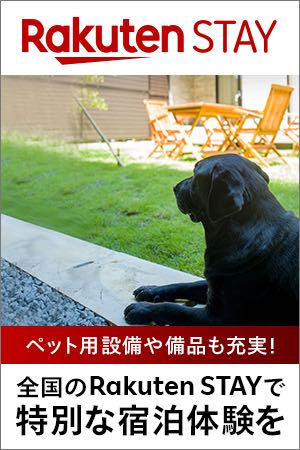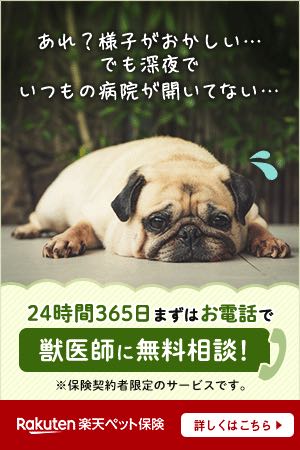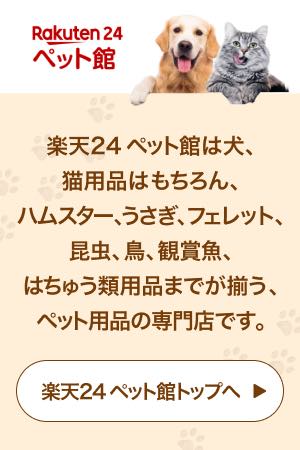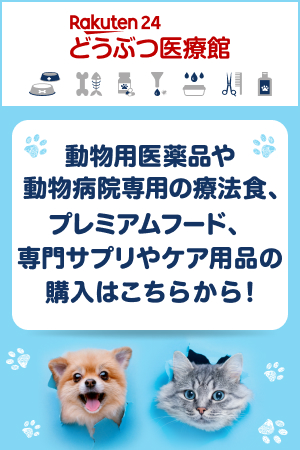犬を飼う前に確認すること
犬に限らず、ペットを飼うことはひとつの命を守るという使命を負うことでもあります。まずは、一度冷静になって、本当に犬をお迎えできる状況なのか考えてみましょう。
・犬を飼える住宅や環境ですか?
・犬を迎えることに家族全員が合意してますか?
・動物アレルギーの心配はありませんか?
・寿命まで変わらぬ愛情と責任をもって飼育する覚悟はありますか?
・世話をする体力と時間はありますか?
・高齢になった犬を介護する心構えはありますか?
・経済的負担は考慮できていますか?
・必要なしつけと、周囲への配慮はできますか?
・ライフステージが変わった際も継続飼養する覚悟がありますか?
・万が一飼えなくなってしまったときのことを考えていますか?
これらの質問に、すべて自信をもって「はい」と言えるようになってから、お迎えをするようにしましょう。
犬を飼う前の準備

出典:https://www.shutterstock.com/
犬をお迎えする前に、お世話にはどのようなものが必要なのか、どのような環境が好ましいのかチェックして、準備しておきましょう。
住環境を整える
家は室内保育が基本です。したがって家の中に、薬や電池、洗剤など、犬が口にして危険なもの、小さくて口に入れてしまいそうなものは、取り出せない場所に片付けましょう。また、フローリングの床は足が滑って転倒などのリスクや関節への負担があるため、カーペットやマットを敷いておくと安心です。
寝床など、犬がくつろいで過ごせる場所を確保して、ケージやサークルを設置しておきましょう。エアコンの風が直接当たったり、直射日光が当たったりする場所は避けて、快適に過ごせることを一番に考えてあげることが大事です。
犬との暮らしに必要なアイテム
犬のお世話に最低限必要なアイテムは、事前に揃えておきましょう。主に、以下のようなものがあります。
・ドッグフード
・犬用の食器
・トイレ、トイレシーツ
・ケージ、サークル
・クレート(キャリーケース)
・おもちゃ
・首輪、リード
・グルーミンググッズ
これらのアイテムは、実際に使ってみないと好みが分からない場合もあります。おもちゃなど、さまざまなタイプが販売されているアイテムについては、日々の様子を見て、買い替えてあげるか、複数のタイプを準備しておくようにしましょう。
かかりつけの動物病院を探しておく
犬は、自分で体調不良を訴えることができません。体調の変化に気づけるかどうかは、飼い主さんにかかっています。しかし、本当に受診が必要な状態かどうかを判しづらい場合、対応に困ることもあるでしょう。
そんな時でも、気軽に受診できるかかりつけの病院があると、とても頼りになります。なお、動物病院にも休診日があるため、いざという時のために複数のかかりつけの動物病院を確保しておくと安心です。
うちのこ初日(お迎え当日)
犬は、初対面の人間にもフレンドリーに接してくれる子も多いですが、新しい環境になじむまではストレスを感じることも珍しくありません。特に、これまで母犬と一緒に暮らしてきた子犬は、母犬との離別でストレスも大きくなっている可能性があります。
新しい場所、嗅いだことのない匂い、聞き慣れない音など、犬が落ち着くまでに少し時間がかかります。迎えた日は、嬉しくてたくさん触ってコミュニケーションをとりたいと思うかもしれませんが、できるだけ静かに過ごせるように配慮しましょう。
犬のしつけ

出典:https://www.shutterstock.com/
犬のしつけは、人間とともに暮らすためのマナーを覚え、飼い主との信頼関係を深めるために必要不可欠です。犬が誰かを傷つけるといったトラブルを防ぐためにも、必ずしつけは行いましょう。
トイレ
トイレのしつけは、特に重要です。犬は、猫とは違い、トイレを覚えるまでにトレーニングを要します。トイレがしつけられないと、家中の至るところで排泄してしまうようになります。
ハウス
犬が、ケージやクレートなどで過ごせるようにトレーニングすることで、飼い主が不在の際の事故防止や環境が変わった際の居場所の確保ができるようになります。
指示しつけ
「まて」「伏せ」「お座り」などの指示しつけは、犬や周囲の人間の安全を守ることにつながります。犬が突発的に飛び出した時に立ち止まらせたり、興奮して人間に飛びかかろうとした時に抑制したりすることができます。
アイコンタクト
アイコンタクトは、犬が飼い主の方を見て、目を合わせることを指します。目を合わせることで、これから飼い主の言うことを聞ける体勢をつくることができるため、初期の段階で覚えておきたい重要なしつけと言えます。
犬のごはん・おやつ
犬をお迎えした初日から、ごはんの用意は必要ですよね。どのようなごはんを用意しておけば良いのか、ポイントをご紹介します。
新しい環境に慣れるまでの犬のご飯
犬のごはんは、月齢・年齢によって食べられるものが異なります。したがって、犬をお迎えした時の成長段階に応じたごはんを用意する必要があります。さらに、新しい環境に慣れるまでは食がすすまない子も多いため、ペットショップやブリーダーさんがあげていたものと同じものを与える方が無難です。環境に慣れるとともに、徐々に切り替えていきましょう。
おやつをたくさん与えるのはNG
犬用のおやつは、とても種類が豊富で嗜好性が高いものが多いため、つい喜ぶ様子が見たくてあげすぎてしまうという飼い主さんが多いです。しかし、栄養バランスが偏ったり、肥満につながったりするリスクがあるため、おやつはしつけのご褒美として少しあげる程度にとどめましょう。
狂犬病の予防接種や混合ワクチン

出典:https://www.shutterstock.com/
犬の健康や周囲の人の安全を守るために、予防接種や混合ワクチンのスケジュールを確認しておきましょう。
狂犬病の予防接種
狂犬病の予防接種は、年1回、義務化されています。狂犬病は治療法がない病気で、発症すると命を落とすため、犬も人も守るために必ず受けなければなりません。動物病院や、自治体が実施する集団接種で受けることができます。
犬の混合ワクチン
混合ワクチンは、発症すると致死率の高い犬ジステンパーや、人にも感染するレプトスピラ症などが予防できるもので、任意接種ではありますが受けておいた方が安心です。ワクチンの種類や年齢によって接種のタイミング等は異なるため、かかりつけの動物病院で相談しましょう。
犬のお手入れ

出典:https://www.shutterstock.com/
犬のお手入れは、健康を保つ上で重要です。病気の早期発見につながることもあるため、こまめに行ってあげましょう。
ブラッシング
ブラッシングは、被毛をきれいに保つだけでなく、皮膚に適度な刺激を与えて新陳代謝を高めるなどの効果があるとされています。基本的に、頭から尻尾にかけて、毛流れに沿ってブラシをかけましょう。
シャンプー
皮脂やフケを洗い流して、皮膚を清潔な状態に保つために、定期的にシャンプーをしてあげましょう。毛玉がある場合は、シャンプーをする前に毛玉を解いておきます。また、足の付け根や内股の部分、足先など、シャンプーの洗い残しがないように気を付けましょう。
歯磨き
歯周病の予防のために、毎日の歯磨きを習慣化しましょう。犬用の歯ブラシはさまざまな種類がありますが、抵抗が強い場合はガーゼを指に巻き付けて慣れさせていくのも良いでしょう。
爪切り
屋外をよく歩く犬はあまり心配がないかもしれませんが、固い場所をあまり歩かない犬は爪が伸びすぎてしまうことがあります。伸びているようであれば、犬用の爪切りで切りましょう。なお、爪の内側に見えるピンク色の部分は血管です。切る時は、血管に触れない範囲で慎重に行い、やすりをかけて、爪の角を取りましょう。
耳掃除
耳掃除は、外耳炎や耳ダニの感染予防につながります。特に、垂れ耳の犬種は蒸れやすく、炎症を起こしやすいため注意が必要です。イヤークリーナーとコットンを使って、優しく拭き取ってあげましょう。
犬の避妊・去勢手術
犬の避妊・去勢手術を受けるかどうかは、飼い主さんがしっかりと考えて決める必要があります。最近は、望まない出産を避けるだけでなく、一部の病気の予防にもつながるとして避妊・去勢手術を勧められることもあるようです。かかりつけの動物病院でしっかりと説明を受けて、メリットとデメリットの両方を踏まえて決断しましょう。
犬のお散歩やお出かけ

出典:https://www.shutterstock.com/
猫とは違い、犬は基本的にお散歩をしてあげる必要があります。単なる運動だけでなく、その他のメリットや目的もあるため、その重要性をよく認識して一緒に歩いてあげましょう。
お散歩
犬にとって、お散歩は、単なる運動や気分転換だけではありません。散歩をすることで、筋力がつき、体力もアップします。また、色々な場所に出掛けることで経験値が上がり、自信につながります。さらに、犬の探求欲求や、テリトリーを確保するという欲求を満たすことにもつながります。
お散歩のマナーを守るために、排せつ物を処理する袋や水、飲み水を持参しましょう。
お出かけ
お散歩ができると、お出かけの幅も広がってきます。犬と一緒に泊まれるホテルやドッグラン、ショッピングモールなど、飼い主さんとの時間がたくさん増えることにもつながるでしょう。お出かけでは、いつものお散歩アイテムの他に、抜け毛防止のための服や自家用車での移動時に使うクレート、犬用ベッドなどがあると便利です。
犬のおもちゃ

出典:https://www.shutterstock.com/
犬のおもちゃは、狩りの擬似体験による本能的な欲求を満たしながら、飼い主さんとのコミュニケーションを図るアイテムとしても役立ちます。どんな遊びを好むのかは、性格にもよるため、複数のタイプを用意しておくと良いでしょう。
また、固さや大きさは、犬の年齢や犬種によって適したものが異なります。月齢・年齢、体重・体格に見合ったものを選びましょう。さらに、犬用のおもちゃは強度も大事なポイントです。すぐにボロボロに壊してしまい、破片などを飲み込んでしまうと健康を損ねる原因になります。
できるだけ、誤食につながらないような安全性の高い素材でできたおもちゃをおすすめします。
犬のお留守番
「犬を一人ぼっちにするのは可哀想」という意見もあるかもしれませんが、実は犬にとってお留守番をすることはとても重要です。お留守番ができなければ、飼い主さんの外出が困難となるため、必要不可欠なことと捉えておきましょう。
犬は、飼い主さんのいない間、ゆっくりと休む時間をとり体力を回復させ、それがストレスの軽減にもつながっています。飼い主が側にいると、どうしても興奮状態になってしまう子も多いため、こうした休息の時間は必要です。
お留守番のトレーニング方法
子犬期の頃は、食事回数をこまめに分ける必要があり、長時間お留守番をさせることはあまり望ましくありません。もともと群れで暮らす犬にとって、単独で過ごすことは慣れないうちはストレスにもなります。
犬の成長に合わせて、まずは短時間から徐々に延ばしていくつもりでお留守番のトレーニングをしていきましょう。いきなり何時間も留守にすると、大きな不安感をおぼえ吠え続けるなどの行動につながることがあります。安全性を高めるためには、大きめのケージやサークルを用意するのがおすすめですが、自由に動ける方がストレスにならない子もいるため、様子を見ながら試していきましょう。
留守中の環境にも注意
ケージやサークルの中で留守番をさせる場合は、十分な広さを確保しましょう。寝床とトイレが近すぎると、排泄を我慢してしまうこともあるため、注意が必要です。
留守番中の居場所から窓の外が見えると、その都度反応して落ち着かなくなる可能性もあります。直射日光から避けるという意味でも、窓から離れた場所をおすすめします。
フリーで留守番させる場合は、置いてある物にも注意しましょう。コード類はかじってしまわないようにカバーをする、飲み込んでしまいそうな小さなものは片付けておく、生ゴミなどは取り出せない場所に置いておくなどの配慮が必要です。
犬のペット保険
ペット保険とは、ペットが病気や怪我をして治療を受けた時に、治療費の一部を補償するための保険です。
人間は、公的な健康保険によって、治療費や薬代の負担は少なくて済むようになっていますが、動物にはこのような制度がありません。治療が必要な時は、全額自己負担となり、場合によっては高額な費用を要します。
ペット保険は、万が一の時に、治療費の心配を軽減することができるというメリットがあります。愛犬の健康をしっかりと守るために、ペット保険に加入しておくと安心でしょう。
災害時の備え

出典:https://www.shutterstock.com/
日本に住んでいると、自然災害への備えはもはや必要不可欠です。自分自身だけでなく、愛犬の安全もしっかり守れるように備えておきましょう。
犬用の防災グッズをまとめておく
自然災害は、予測できないものも多いです。速やかに避難できるように、犬用の防災グッズはまとめて置いておき、すぐに持ち出せるようにしておきましょう。特に、以下のようなものがあると便利です。
・ドッグフード(最低3日分)、飲み水
・特別非常食
・食器
・クレート、キャリー、ケージ
・トイレシーツ
・ビニール袋、マナーポーチ、消臭スプレーなどのエチケット用品
・トイレットペーパー
・首輪、ハーネス、リード
これらのアイテムは、日頃から使っているものが大半ですが、既にあるからといって有事の際にかき集めるのはおすすめしません。災害用に一式まとめて保管しておくと良いでしょう。
マイクロチップ、迷子札
マイクロチップとは、2022年からブリーダーやペットショップ等で販売される犬に装着が義務付けられているもので、獣医師が注入器を使って皮下に埋め込みます。個体識別番号を読み込めば、飼い主の所在地などの情報が出てくるため、迷子になった時に役立ちます。
譲渡される犬については、今のところ努力義務となっているため、すべての犬が装着済みというわけではありません。災害時や迷子になった時のことを考えて、マイクロチップを入れておくと良いでしょう。
迷子札は、ネームプレートのようなもので、飼い主の連絡先を記載し、首輪等につけておきます。マイクロチップと併せて備えておくことをおすすめします。
指定避難場所の確認
避難する時に、どこに行ったら良いのか分からない、といったことがないように、近隣の指定避難場所を確認しておきましょう。加えて、犬と一緒に避難できるのかどうか、避難先では犬はどう過ごすのかについても聞いておくと安心です。
避難訓練をしておく
災害時は、1秒でも早く安全な場所へ逃げることが大事です。愛犬の命を守るために、避難訓練をしてシミュレーションしておきましょう。集合住宅の場合は、玄関以外の出口からの避難方法も押さえておく必要があります。
まとめ
犬との暮らしは、私たちに幸せな時間をたくさんもたらしてくれるでしょう。しかし、犬をお迎えするためには、さまざまな覚悟も必要です。最後まで、ひとつの命を守りきるにはどんな心構えが必要なのかをあらかじめよく考えてから決めていきましょう。犬のために用意するべきものもたくさんあります。ぜひ、準備をしっかりして、犬をお迎えしてあげてくださいね。