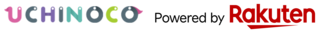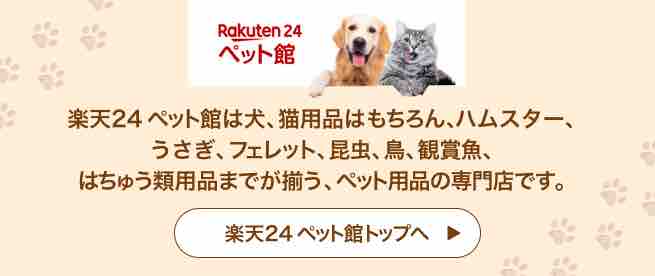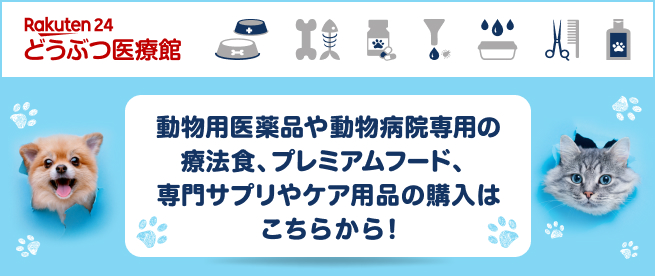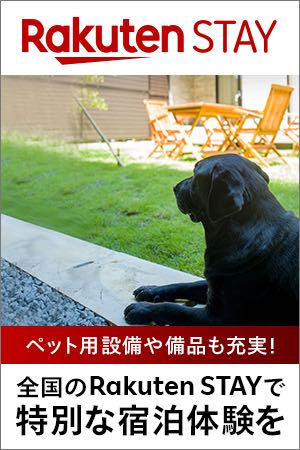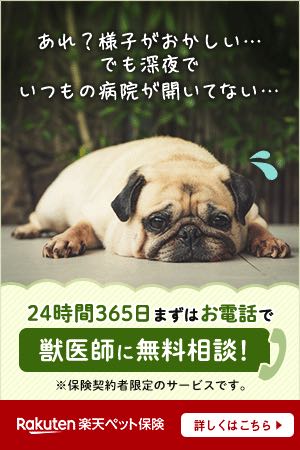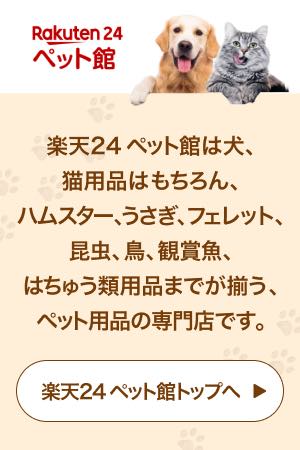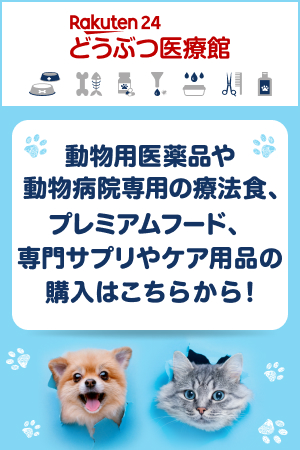猫の脱走防止策

出典元:https://www.shutterstock.com
猫はもともと好奇心が旺盛です。中でも特に若い猫は、外の世界に興味を持って脱走してしまうことがあります。
これは元野良猫だけでなく、生まれた時から室内で飼っていたとしても起きることです。
本能などから憧れの外に出てしまった猫ですが、外は思った以上に広く、まず迷子になります。後悔しても時すでに遅しで、ほかの猫の縄張りにうっかり入ってケンカになったり、咬まれて病気をうつされたり、車に轢かれてしまうといった多くの危険が待ち受けています。
そんな悲しいことにならないように、脱走防止をしっかりと行っておきましょう。
玄関からの脱走防止策

出典元:https://www.shutterstock.com
最も脱走される確率が高いのが玄関です。猫は動きもすばやく、窓や玄関が少しでも開いていると、スルリと出てしまいます。その上、賢いので、前足を器用に使って戸を開けてしまう猫もいます。
玄関に内ドアをつける
玄関前に柵や簡易ドアを設置すると安心です。
突っ張り棒タイプの扉やパーテーションなら工事の必要もなく、自分でかんたんに取り付けることができます。ただし、猫は高くジャンプすることができるので、高めにしないと乗り越えられてしまいます。
脱走防止用アイテムとして売られているものもありますし、フェンスやゲートなどを利用しても取り付けることができます。ただ、引き戸タイプだと開けられてしまう恐れがありますので、注意が必要です。きちんとしたものをつけたいときはリフォーム業者に依頼しましょう。
ドアストッパーをつける
猫はドアノブを下げたり、引き戸も難なく開けてしまいます。
こんなときはドアストッパーをつけるのが◎。猫が通れる幅だけ開けておくこともできますし、閉めておくときは下げておくことで、たとえドアノブを下げてしまったとしても、かんたんには出られなくなります。
ドアロックをつける
ドアノブをかんたんには下げられないようにノブを固定できるものが市販されています。また、差し込むだけで簡単にドアストッパーになる引き戸ロックというものもあります。
窓からの脱走防止策

出典元:https://www.shutterstock.com
空気を入れ替えるために窓を開けたら、そのまま猫が出て行ってしまったということはよくあることです。また、網戸があるからと安心してはいけません。網戸も開けてしまうのが猫なのです。
まず、網戸のロックをつけるようにします。
ただ、網戸を破ってしまうこともあるので、耐久性の強い網戸に付け替えたり、網戸自体をペット用に変えるというのも手です。また、窓枠にフェンスや猫の脱走防止柵をつける方法もあります。
工夫次第では100均で売っている突っ張り棒や棚を利用しても作れます。
窓はリビングや寝室ばかりではありません。見逃しがちなお風呂やキッチンの小窓も開けっぱなしにしておけば、猫にとっては脱走するには十分な大きさです。
「うっかり」が「残念なこと」にならないよう十分に気をつけましょう。
ベランダからの脱走防止策

出典元:https://www.shutterstock.com
たまには外の空気を吸ってもらいたいとベランダに出してあげるのはいいのですが、ベランダなら安心ということはありません。人間なら不審者以外の出入りはありませんが、猫はたとえ高層マンションであっても自分が何階に住んでいるという自覚はありません。
手すりから誤って落ちてしまうこともありますし、また、すき間を通って外へと出てしまうこともあります。
ベランダに出すなら、フェンスやパーテーションを設置したり、シェードやネットを張って出られないようにしてから出すようにしましょう。
ドアや窓の開閉のたびにヒヤヒヤせずに、前もってあらかじめ脱走防止策を講じておくのが賢明です。猫が安全に過ごせるようにするには、猫がやりそうなことを予測し、対策を取ってけがや事故から守ってあげましょう。
著者情報

UCHINOCO編集部
UCHINOCO編集部では、ペットに関するお役立ち情報をお届けしています。